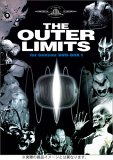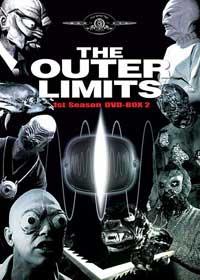| �b�� |
�^�C�g�� |
�R�����g |
DVD |
| ��1�b |
�F���l����
�gThe Galaxy Being�h
�@�@�ēF���C�X�E�X�e�B�[�����X
�@�@�r�{�F���C�X�E�X�e�B�[�����X |
�@�u�����TV�̌̏�ł͂���܂���E�E�E�v�L���Ȏ�R�����̃i���[�V�����Ŏn�܂邱�̃V���[�Y�A���b�͂��̏o��������̂Ȃ����TV�̉摜����n�܂�B
�@�ŏ��Ȃ̂ł������ɋC���������Ă���B�F���l�̑��`���َ��ŁA��͂�A�����J�Ɠ��{�ł͉F���l�ɑ��銴�o���Ⴄ�A�Ǝv�����B���{���ƍ����Ƃ���ނƂ��A�����ƂȂ��݂̂��郂�f�����g���Ǝv�����E�E�E�A�����l���Ă邩������Ȃ��ۂ��ڋʂƁA�@�������Ȃ����`�͊���̈ړ������ۂ��Ă���B
�@���̈ٗl�ȉF���l��TV��M���āA�����Ȃ��Ƃ肩�炾���荇���Ă����ߒ������J�ɕ`����Ă���B���̌��ʁA�F���l���_�f�z�ł͂Ȃ����f�z�A�G�l���M�[���͓d���g�낢�����Ƃ�������B�ƂĂ����݂��̊��ł͐����ł��������Ȃ����E�E�E
�@�o���́u�A���W���[�m���ɉԑ����v���f�扻�����M��́u�܂�������N�Ɂv�Ō�Ƀr�f�I�ł͂���ς�u�A���W���[�m���ɉԑ����v�ɉ��肵������u�`���[���[�v�ŃA�J�f�~�[�܂���܂����N���t�E���o�[�g�\���B
�@�O���͒n�������㔼�͑�|����ȓ��B�B
|
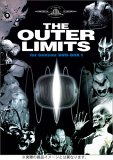
VOL.�P |
| ��2�b |
������l�̎���
�gThe Hundred Days of the Dragon�h
�@�@�ēF�o�C�����E�n�X�L��
�@�@�r�{�F�A�����E�o���^�[
�@�@�@�@�@�@���o�[�g�E�~���c |
�@�����Ȃ�n���Șb�E�E�E�B�X�p�C����ł���B�O�O�V�́w�S�[���h�t�B���K�[�x�A���{�́w�L���O�R���O�̋t�P�x�Ȃǂ����Ă������邪�A�U�O�N�㓌�m�̖^���͖����ɓG�������B���͋C�͂�����Ɓw�e�Ȃ��_���ҁx��f�i������BTV�ɂ�������炸�A�����f���ɂ͐[�݂�����A�e�̋������ς�҂�s���ɂ�����B
�@�J�����́w�����Ɍ������Č��āI�x�w�A�����J���E�r���[�e�B�[�x�w���[�h�E�g�D�E�p�[�e�B�V�����x�łR�x�A�J�f�~�[�܂��Ƃ����R�����b�h�E�z�[���B
|
| ��3�b |
�䂪�߂�ꂽ���E����
�gThe Architects of Fear�h
�@�@�ēF�o�C�����E�n�X�L��
�@�@�r�{���C���[�E�h�����X�L�[�@�@ |
�@�V���[�Y���A���𑈂��ُ�Șb�B�ǂ���������������̂�������Ȃ����A�Ȋw�҂������W�܂��āA�푈���Ȃ������߂ɂ͐l�ދ��ʂ̓G�����˂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������ƂʼnF���l���n���ɏP������A�Ƃ����������f�b�`�グ�悤�Ƃ���B�����������f�}�𗬂������ł͕s���Ȃ̂Ől�Ԃ�{���̉F���l�ɉ������邱�Ƃɂ���B���������Ă���Ȍv��Ɏu�肷��l�͂��Ȃ��Ǝv�����B�قƂ�ǂ̎��Ԃ��l�̉����̗l�q�ɔ�₳��A�Ō�̍Ō�Ɍv�悪���s�Ɉڂ����̂����E�E�E���̉F���l���l�ԂɎ��Ă������Ȃ��Ƃ����̂��������B
�@�ē̓o�C�����E�n�X�L���B
|
| ��4�b |
�l�ԓd�r
�gThe Man with the Power�h
�@�@�ēF���Y���E�x�l�f�N
�@�@�r�{�F�W�F���[���E���X |
�@���̖M��͂�����Ə����Ⴄ���A�]����������s���A���\�͂��������j�̔ߌ���`���B���̑�w��������S���X�ł͂Ȃ��A���i�͍Ȃɓ��̏オ��Ȃ��I�h�I�h�������S�Ȓj�Ȃ̂��ʔ����B������h�i���h�E�v���U���X������ȏ�Ȃ��͂܂���B
�@���̏��S�Ȓj���A�����ނ������Ƃ�����ƁA�ǂ�����Ƃ��Ȃ����_�i����ǂ������̃}���K�w���łɃg���`���J���x�ɏo�Ă���h�������_�݂����Ȃ�j�����N���N�ƗN���オ��̂ł������B
|
| ��5�b |
�������i��
�gThe Sixth Finger�h
�@�@�ēF�W�F�[���Y�E�S�[���h�X�g�[��
�@�@�r�{�F�G���X�E�Z���g�E�W���Z�t |
�@�����l�������ł����Ƃ����C���[�W�ՓI�ɂ����L���ȍ�i�B�f�r�b�h�E�}�b�J�������o���B�Ȃ��͋C���ς��Ǝv������A�ꉞ�C�M���X������B����Ŗ��m�ŕn�R���Y�z�v�Ƃ������Ƃ炵���B���ς�Ƃ�⍷�ʓI�B�����l���s�A�m��e���V�[���������B�����Ƃ���}�b�J�������{���ɒe���Ă���B���l���̃W���E�n���[�Y���ǂ��B
|
| ��6�b |
���܂�Ă��Ȃ������j
�gThe Man Who Was Never Born�h
�@�@�ēF���i���h�E�z��
�@�@�r�{�F�A���\�j�[�E���[�����X |
�@�w�P�Q�����L�[�Y�x�݂����Șb�B�Ȋw�I�ݒ�͂��Ȃ肢�����������A���b�Ƃ��Ċ�����Ă݂�Ƃ��Ȃ�̌���B
�@���Ԃ̕ǂ�j���ĂQ�O�O�N��̒n���ɗ��Ă��܂����F����s�m�́A�r�p�����n���ɜ��R�Ƃ���B������l�����c�����n���l�A���h���i�}�[�e�B���E�����h�[�j�͌��B�o�[�g�E�L���{�b�gJr.�ƌ����Ȋw�҂��F�����玝�����ۂ����B���A�l�ނ͖ŖS�����B�ߋ��֖߂��ăL���{�b�g���E���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�ƁB�A���h���͂��̍ۂ̂��߂ɗe�p�������ɂȂ�Ȃ����炢�X���ϖe���Ă����A���]�͖����������B�u�d�v�������̂͗\�h��w���������A�l�ނ͌��֍s�����Ƃ�A�������̐����ɖZ���߂����̂��B�v
�@�����ĉߋ��ɖ߂����A���h���́A�L���{�b�g�̕�ɂ�����Ⴂ�����m�G���ɑ������邪�E�E�E�B
�@�A���h���ɂ͍Ö��\�͂�����i�Ȃ��H�j�A�l�X�ɂ̓n���T���Ȓj�Ɍ����Ă����i�����h�[���f��ʼn�����킯�ˁj�B���̎�������ʂ��\�t�g�t�H�[�J�X�Ȃ̂����܂����o�B�����̏X���e�e��p���A�m�G���������n�߂�A���h���̕��G�ȓ��ʂ������h�[�͉��������Ă���B�������ł���B
|
| ��7�b |
�n���͑_���Ă���
�gO.B.I.T.�h
�@�@�ēF�Q���h�E�I�Y�����h
�@�@�r�{�F���C���[�E�h�����X�L�[ |
�@����̑唼���ؐl�̎��^�ɔ�₳��Ă���A�n���Ƃ������A��b�͌��\����ł���B���������Ƃ��̃V���[�Y�͎q����Ώۂɂ��Ă��Ȃ��ƕ�����B
�@���h�Ȃ̈ϑ����Ă���Ȋw�������ŁA�E�l�������N����B���Ԃ��d���������{�͏�@�c���I�[���B����h�����A���Ԓ������s���B���̌������̉Ȋw�҂��������_��a��ł����B�₦������ꂢ��悤�ȋC������A�l�I�Ȕ閧���ǂ�ǂ�R��Ă���E�E�E�Ə،�����B�ȑO����s����i���Ă����Ȋw�҂͓�ւ���Ă����B�����ċc���͂���@�B�̑��݂�˂��~�߂�B���h�Ȃ̈˗��ŊJ������O.B.I.T�Ƃ����@�B�������E�E�E�B
�@�ʔ����ዾ����������̒j�A���}�b�N�X���m���������W�F�t�E�R�[���[�͂T�O�N��Ƀ��b�h�E�p�[�W�Ɉ���������A�s�����������Ă����l���������ŁA�m����ALL�@CINEMA�@ONLINE�Ō�������ƂP�Q�N�̃u�����N������B��ɉ����̋��t�Ƃ��ăW���b�N�E�j�R���\���A���i�[�h�E�j���C�A�T���[�E�P���[�}���A�o�[�u���E�X�g���C�T���h�A���r���E�E�B���A���Y�Ȃǂ̎w�������������ł���B���̘b���Ԏ��̎���܂��Ă���͖̂��炩���낤�B
�@�R�����b�h�E�z�[���ɂ��f�����Â�܂���ŁA�l���ɂ��w�i�ɂ��قƂ�ǂ܂Ƃ��ȏƖ����������ĂȂ��B
|
| ��8�b |
�]����
�gThe Human Factor�h
�@�@�ēF�A�u�i�[�E�r�o�[�}��
�@�@�r�{�F�f���B�b�h�E�_���J�� |
�@�k�Ɍ��̕X�ɕ����ꂽ�R����n�B���������̂Ŏ��Ȃ����߈�������A���_�Ɉُ���������������A�w�b�h�M�A�݂����ȖX�q�����Ԃ�ƁA�]�g��d�g�ɂ��Ă��݂��̍l���Ă��邱�Ƃ��킩�鑕�u���J�������Ȋw�҂̃X�g�[���[���������ĂƂ�ł��Ȃ����ԂɂȂ�Ƃ����b�B
�@�ȒP���ɂ����Ƒ�ѐ�F�ḗw�]�Z���x�T�X�y���X�ŁB���܂ЂƂb�����Ȃ�Ă��Ȃ���ہB���������錶�o�����ʓI�Ƃ͎v���Ȃ��B�Ȋw�҂������鏕��Ƀ��o�[�g�E�A���g�}���g�̃T���[�E�P���[�}���B
|
| ��9�b |
�F���r�[���X�̐N��
�gCorpus Earthling�h
�@�@�ēF�K�[�h�E�I�Y�����h
�@�@�r�{�F���C�X�E�V�����{�j���[ |
�@������ׂ�Ƃ������\�Ԕ����Ȑݒ�őO���͖��f���邪�A�㔼���̐̐�����������B��̒j�i�푈���̕����œ��W�ɋ��������Ă���̂����A���ꂪ���W�I�݂����ȍ�p������炵���j�������͓������������Ȃ����̂ł͂Ȃ����H�ƔY�݃��L�V�R�ɓ������邠���肩��]���r�f����ۂ��Ȃ��Ĉٗl�ȕ��͋C�ƂȂ�B�Ƃ���ŗ��̃n���E�b�h�f��̃��L�V�R�ς����Ă݂�Ƌ����[����������Ȃ��B
�@�{�y�̐l�Ԃ�����ɑ��Ď�O����Ȋy�����C���[�W����̂Ǝ��Ă���悤�ȋC������B�����͕`���Ă��Ȃ����A�������Ƃَ͈��Ȏ�p�I�ȉ�H�œ����Ă���A����ȃC���[�W�ł���B
|
| ��10�b |
����
�gNightmare�h
�@�@�ēF�W�����E�A�[�}��
�@�@�r�{�F�W���Z�t�E�X�e�t�@�m |
�@�l�Ԑ��������Ԃ��Ă��܂��R���g�D�ɑ���{��A�X�g�[���[�̊����x���猩�Ă����x���̍�������B�n���̓G�{�����Ɛ푈�����Ă����B�U�l�̕��m���G�{�����l�̕ߗ��ƂȂ�B�G�{�����l�͈�l��l�Ăяo���Ēn���R�̋@����b���Ƃ��܂�B�G�{�����l�͌��o�𗘗p���ނ��S���I�ɒǂ��l�߂�B����ł������S�����������Ȃ��ނ炾���A���̊Ԃɂ��ɔ����G�ɒm���Ă��܂��B�N�����������̂��E�E�E�^�S�ËS���璇�Ԋ��ꂪ�n�܂�A���_��a��ł����B�����ĈӊO�Ȍ������E�E�E�B�w�P�Q�l�̓{���j�x�̂悤�ɁA�X�n�̃X�^�W�I�ɏ�������̊₵���Ȃ��Ƃ������ۓI�ȃZ�b�g�ŁA�j�����̐[�w�S�����ނ��o���ɂȂ��Ă������܂͔��͂�����A�o�D�ɑ����̉��Z�͂�v������B���ɐ��_�I�ɋ���ł₽��Ⴆ������}�[�e�B���E�V�[���ƁA�����ő����������Ă���悤�ȑԓx�̃W�F�[���X�ɓc�i�w�_�C�E�n�[�h�x�̎В��̐l�j�̑Δ䂪�ʔ����B
|
| ��11�b |
�l�_
�gIt Crawled Out of the Woodwork�h
�@�@�ēF�K�[�h�E�I�Y�����h
�@�@�r�{�F�W���Z�t�E�X�e�t�@�m |
�@�Ƃ��錴�q�͌�������K�₵���Ȋw�҂́A�̂ɕςȋ@�B�����t���������Ɉē������B�ē����ꂽ�̂͘L���݂����ɍג��������B�u���A����́E�E�E�v�ƐU��Ԃ������ɂ͂��������K�`�����ƕ܂��Ă����B�����߂�ꂽ�̂��B���Α��̔����J���ƈٗl�ȃ��m���o�Ă���B���d�����_�̂悤�Ȃ��̂������Ă���B�܂�Ő����Ă���悤�ɁE�E�E�B
�@�l�_�ƁA������l�^�������ł����A���̓������܂�֘A�����Ȃ��Ƃ������A���̃l�^�łQ�{�����Ȃ����Ǝv�����B���̕ӂ��P���Ԃ��̂̂炢�Ƃ���ŁA��͂�P���Ԃ�������r�{����̂͑�ς��Ȃ��A�Ǝv���B�Y�����̃G�h���[�h�E�A�X�i�[���ǂ��B |
| ��12�b |
���̐��E��
�gThe Borderland�h
�@�@�ēF���X���[�E�X�e�B�[�����X
�@�@�r�{�F���X���[�E�X�e�B�[�����X |
�@����͎q���̍����ĂĖ��Ɉ�ۂɎc�����B���e�͂܂����������o���Ȃ��������A�u����Ƃ��E���v���o���Əo���ꂽ�V�[�������\�V���b�N�������B���炭�̊ԁA�u����Ƃ��E�肾�����璃�o�Ɣ����ǂ�����Ă��H�v�Ƃ����낢��l������B������̍r�ؔ�C�F�������Ԃ����ƍl���Ă����낤�B���̐��E����E�ƍl����Ȋw�ҁA��}�t�A�S���������q�ɉ������S�̕x���̎O�҂̎v�f���A��|����Ȏ�������Ō�������r�{�͂Ȃ��Ȃ���������������B
�@�v���f���[�T�[�̃��X���[�E�X�e�B�[�u���X������ēA�r�{��S�������B���͎Ⴂ���A�I�[�\���E�E�F���Y�̎g����������Ă��������ł��B |
| ��13�b |
���Â̋�
�gTourist Attraction�h
�@�@�ēF���Y���E�x�l�f�B�N
�@�@�r�{�F�f�B�[���E���[�Y�i�[ |
�@��ăT���u���X���a���i���Y�i�R�[�q�[�A���p��X�y�C����j�̓}�L�����I���R�i�w�����[�E�V�����@�j���N�Ղ���R���ƍٍ��������B�����Ƃƈꈬ��̍������x��Ɛ肵�B���鏊�ɓ����A�X�p�C���z������A���O�͕n�������_�̎��R�͂Ȃ������B
�@���̍��̌Ő����T���@�̎������s���Ă������ƉƂ̃f�N�X�^�[�͊C��Ŋ���Ȑ����ɏP���A�����ߊl����B���̐����͌Ñォ��C���f�B�I�����q���Ă���_���Ƃ������肾�����B�����m�������R�͂��̐�����Ɛ肵�悤�ƕ��͂������ĉ������邪�A���̐����͏펯����\�͂������Ă����E�E�E�B
�@���̉����ƃw�����[�E�V�����@�̖ʍ\�������ł��������B�����̑��`�͂������Ƃ��������悤���Ȃ��B�����ٗl�ɂł������̒�����݂ɐl�Ԃ�����A���葫�͊O�ɓ˂��o���Ă��āA���̎葫�Ŕ���������B�l�Ԃ������Ă��邱�ƈ�ڗđR�ŁA�ǂ��l���Ă��q�����܂��Ȃ��A���ꂾ�����X�ƌ�������ƁA���̊Ԃɂ������͂��o�Ă��邩��s�v�c�ł���B�R���p�̃w�����[�V�����@�̊������ɝh�R���邾���̔��͂�����B
�@�������������Ŗ\���V�[���́w�K�����@����b��x�̃M���I�X���v���o�����B���̌�w�E���g���p�x�̊C��l���S���݂����ȓW�J�ƂȂ�A�Ō�̓W�����E�u�A�}���ḗw�G�������h�E�t�H���X�g�x�݂����ȃA���Ƌ����������}����B�����Ɛl�Ԃ��{���̐����Ŋi������V�[���i���̐l�͑�ρj������A�Ȃ��Ȃ������̑�����i�ł���B |
| ��14�b |
�a�l�̋��|
�gThe Zanti Misfits�h
�@�@�ēF���I�i���h�E�z�[��
�@�@�r�{�F�W���Z�t�E�X�e�t�@�m |
�@�ӂƎv�����A���̃V���[�Y�̖M��̓l�^�o���������B�m���ɐ̂̓l�^�o���ɂ��Ă͊��e�������B�\���҂ł����\�Ō�̕��܂Ő�����������Ă�����Ȃ��B�Ƃɂ����a�݂����ȃU���f�B���l���o�Ă���L���ȍ�i�B
�@�ČR�͎s���ɋɔ�Ŏ��͉F���l�ƃR���^�N�g�������Ă����B�U���f�B���l�͂��̐��̋����Ƃ̗��Y�n�Ƃ��āA�����J���t�H���j�A�̍x�O�̍����̈ꕔ�𖾂��n�����Ƃ�v�����Ă����B�W�Q����Βn���S�̂�j��i�C�͊O���H�j�ƌ����̂�����]�킴��Ȃ��B�U���f�C��������w��������������A���̗�����֎~�n��ɓ��S���̃M�����O�i�u���[�X�E�_�[���j������Ă��āE�E�E�B
�@�O��ɑ����Đ��i�ُ�ƍߎҖ��̓��ӂȔo�D�̓o�ꂾ���A�u���[�X�E�_�[���̎g�����͂��������Ȃ��B��̉��̂��߂ɏo�Ă����̂��E�E�E�B�U���f�B���l�̓R�}�B��œ����A�\�Z�̓s����o�ꎞ�Ԃ͏��Ȃ�������Ȉ�ہB�݂�ȈႤ������Ă��ăf�U�C�����H�v����Ă���B�����Ƃ�����ȋa���Ȃ�ł���Ȃɕ|���̂��悭�킩��Ȃ����B
�@�N���C�}�b�N�X�ł͑�ʂ̃U���f�C���l����n�ɉ����A�w�G�C���A���Q�x�I�R����ݒ�ƂȂ�B�������U���f�B���l���ɂ́A�l�Ԃɂ͋����Ă��Ȃ��閧�̖ړI���������B�����ɂ��U�O�N��炵������Ȍ������҂��Ă���B�Ƃ�������X�����i���ݒׂ��Ă���ڂ��ɂ��Ȃ��a�ǂ��ɂ����悤�ɐU���邱�Ǝ��̂�����Ȑݒ�Ȃ̂����B
�@�����̍r��̂������i�����������B |
| ��15�b |
�N�������l
�gThe Mice�h
�@�@�ēF�A�����E�N���X�����h�i���D
�@�@�r�{�F�r���E�r�E�o�����W���[
�@�@�@�@�@�@���E�E���[�n�C�� |
�@�w�X�^�[�g���b�N�x�ɏo�Ă���]�����u�������͂���Ȃ��Ƃ����Ă����̂�������Ȃ��B�N�������Ƃ̗F�D���ƂƂ��ĊJ�����ꂽ�u�Ԉړ����u�̐l�̎����Ƃ��āA�P�����_�[���m�͏I�g�Y�̎��l����u��҂���B�E���̃`�����X��_���`�m�i�w�����[�E�V�����@�j���u�肷�邪�A�N�������Ƃ̉A�d�Ɋ������܂��B
�@���Â��v�����A�w�����[�E�V�����@���Ă������炾��Ȃ��B�|����Ƃ��X���Ƃ��ł͂Ȃ��A�Ȃ�Ƃ������E�E�E�l�ԗ��ꂵ�Ă���Č������H���Ɍ��킹��ƃ����E�p�[���}���Ƒo���Ȃ��A���̓�l���R���r�̌Y���Ƃ��A���낵�����낤�ȂƎv���i���オ�Ⴄ�̂��c�O�����j�B
�@�P�R�b�ƈ���āA���l�������ɐl�Ԃ炵����������[�݂̂���l�Ԃ������Ă���A���i�����ȂƊ�����B���X�g�̓E�F�X�^�����B�N�������l�̓N���Q�݂����ȃO�j���O�j�����`�ŁA���������̂����m�l����������O�ςȂ̂��ȂƎv�킹��f�U�C���B�������]������Ă����F���l�������ɂ��Ƃ��̂͂ǂ����Ǝv���B |
| ��16�b |
�ΐ��l�̎���
�gControlled Experiment�h
�@�@�ēF
�@�@�r�{�F |
�@������b��F���l����ςĂ��Ă͂����ł��傤�A�Ƃ������ƂŁi���͗\�Z�������Ȃ��H�j�y���R���f�B���̂��̂����Ԃɓ����͓̂��{�̃E���g���V���[�Y�������ł���B
�@����������̓t���h���b�N�E�u���E���̒Z�҂ɂ��肻���ȁA���x���̍�����i�B
�@�_�C���X�͘H�n���̂����Ȃ������Ƃ͉��̎p�A���͉F���̕Ӌ��n���̊Ď����ł������B�����։ΐ�����h�����ꂽ�G�[�W�F���g�A�t�H�{�X���h������Ă���B�ނ͂��̍��x�ɕ��������ꂽ��͘A�M�ł͌����Ȃ��n���Ɠ��̌��ۂł���u�E�l�v�ɋ����������A�O��I�ɉ𖾂���Ɩ�����B
�@�����œ�l�͂Ƃ���z�e���ŋN�������A�j�̕��C�̔��o���珗���j���ˎE����Ƃ����������ώ@���邱�Ƃɂ���B�u�t�s�@�v�ƌĂ��@�B�i���荇�킹�̍ޗ��ō�����悤�Ȃ��������ȃf�U�C���j�ɂ���Ď���ɉ�����A���������r�f�I�̂悤�Ɍ����̋�Ԃ���A�����߂��A�X���[�Đ����A�ꎞ��~�����肷��̂��B������쓮�����Ă���Ԃ͔ނ�̎p�͐l�Ԃɂ͌����Ȃ��B����͎��ɕ֗��Ȃ�����̂ŁA��������~�����Ǝv�������̂��B
�@���x�����Ă��l�Ԃ̍s���������ς藝���ł��Ȃ��ނ�́A�u�����Ȃ����炱�̎����ɉ�����Ă݂悤�B�v�ƒe�ۂ̒e����ς��Ă��܂��̂ł��邪�E�E�E���̌��ʁA����A���̂ɂ䂪�݂��I
�@�Ƃɂ�����l�̉F���l�i�o���[�E���[�X�A�L�������E�I�R�[�i�[�j�̃{�P�Ɠ˂����݁A�l�Ԃ̍s���ɑ��閳�����Ԃ肪�ʔ����B
�@������̓J�����̃R�}���Ƃ��ŎB���Ă��邪�A�X���[�͔o�D��������蓮���ĉ����Ă��ď킹��B���������ƃX���[�œ������Ă���B������̊Ԃʂɓ����Ă���F���l���ɎB�邽�߂ł���B�����߂��̓J��������Ɖ��Z�̗��������܂��g���킯�Ă���悤���B�ŐV�̋Z�p�Ń����C�N���Ă݂�����i�B
|
| ��17�b |
�j�ł̔�
�gDon't Open Till Doomsday�h
�@�@�ēF�W���h�E�I�Y�����h
�@�@�r�{�F�W���Z�t�E�X�e�t�@�m |
�@�z���[�����̘b�B�O���w�T�C�R�x�A�㔼�́w�����W�F�[���ɋN���������x�݂����B�^����SF�����B
�@�삯���������Ⴂ�J�b�v�������܂�Ƃ����T���Ă���傫�ȉ��~�ɓ]���荞�ނ̂����A�����ɂ͂����ɂ��������Ȑ�����̂�����l�ŏZ��ł����̂������B�����ē@���Ŗ������H����B�����Ēǂ��ė������̕��e�����̉��~�ɗ���B�����Ă��镔���ɒu���Ă��锠�̑O�ɗ��ƁE�E�E�B������i�~���A���E�z�v�L���X�j�̖����Ƃ����A�암�̂��тꂽ���~�Ƃ����A��͂胍�o�[�g�E�A���h���b�`�ḗw�����W�F�[���ɁE�E�E�x��w�ӂ邦�Ė���x�̃x�e�B�E�f�C�r�X�P���Ă���悤�ȋC������B
|
| ��18�b |
�������l
�gZZZZZ�h
�@�@�ēF�W�����E�u���[��
�@�@�r�{�F���C���[�E�h�����X�L�[ |
�@�ǂ��ł��������Ƃ������̃V���[�Y�ɏo�Ă��鏗���������������A�C������B����TV���̂Ƃ������ƂŃX�^�[�o�D���g���킯�ɂ������Ȃ��̂ł���Ȃɔ��l�͂łĂ��Ȃ����A���̍�i�̃W���A���i�E�t�����N�͂Ȃ��Ȃ��d�����Ȕ����A���������ł���B���̏������W�[�i�i���̖��O�ő��̐l�̓s���Ƃ��Ă��܂��̂����j�������w�҃x�����m�̌������ɂ���Ă��Ė�����菕��ɂȂ��Ă��܂��̂ł��邪�A�d�g�Ȍ����ɂ��ւ�炸�A�x�����m�͔ޏ��̖��͂Ɉ������܂�Ă��܂��̂ł������B
�@���̔��m�̌������������B�I�̌��t��������Ƃ����̂��B���I�̔�����M����ނ̔��������I��|��@�ɂ�����ƁA�u�V���j���E�V���n�b�P���v�u�R���Z�R���Z�v�u�A�b�A�E�V���E�V���I�v�Ƃ��|��ł���̂��Ƃ����B����͂����o�E�����K���ǂ���̑����ł͂���܂���B�����Ƃ������������Ƃ�łǂ��Ȃ�H�Ƃ��v���̂����B�Ō�͓��R�I�̌Q�̂��l�Ԃ��P���̂��낤�Ɗ��҂������A���B�ʂł̓`�g��������ȏo���B
|
| ��19�b |
���̂̐N��
�gThe Invisibles�h
�@�@�ēF�W���h�E�I�Y�����h
�@�@�r�{�F�W���Z�t�E�X�e�t�@�m |
�@���錠�͎҂����̂��Ȃ��H���l�ߎ҂��W�߂ČP�����A�Ȃɂ��d�����ȉA�d����Ă�B�v�[�^���[���Ă��̑g�D�ɐ����������{�̃G�[�W�F���g�A�X�y�C���i�h���E�S�[�h���j�͂��̌P�����łƂ�ł��Ȃ����̂�ڌ�����B
�@����N���̒Z�҂ŁA�w���ɏ�����Ċ�����Ɠ����悭�Ȃ�i���̑��茩���ڂ̓Z���V�݂����ɂȂ��Ă��܂��j�Ƃ����F�������̘b�����������A�Ȃ��̃��g�l�^����Ȃ����Ǝv�킹��B�����������l���Ăяo���Ĕw���ɏ悹�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�����A�����������B����ł͐��E���e�̓��͉����B
�@�O���A�A�T�ȌP�����A�㔼�͖��邢���V���g��DC�ƁA��_�ȏ�ʂ̐�ւ����ʔ����B
�@�����ł��R�����b�h�E�z�[���̉f�����Ⴆ�Ă���B���ɑO���̔����Ȗ��Ẫg�[���������B�����ɂ��������鏑�f�B�b�N�E�h�[�\���̃L�����������B
|
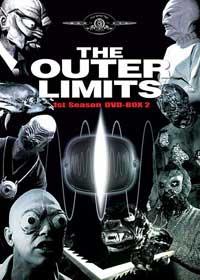
VOL.�Q |
| ��20�b |
�F���ւ̂�����
�gThe Bellero Shield�h
�@�@�ēF�W�����E�u���[��
�@�@�r�{�F���[�E���[�w�C��
�@�@�@�@�@�@�W���Z�t�E�X�e�t�@�m |
����͐��Ԃł͕��̍�i�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���̂��낤���B���܂�b��ɂȂ�Ȃ�����ې[����i�B�Ƃɂ�����l���̃W���f�B�X�i�T���[�E�P���[�}���j�̍s������͂��߂���B����䂦�Ԃ��Č�����������悤�Ɏv����B
�@�^�ʖڂ������[�U�[�J���̌�����ŗ\�Z��H���Ԃ��Ă��郊�`���[�h�E�x�����i�}�[�e�B���E�����h�[�j�͋��~�Ȏ��Y�Ƃ̕��e�i�j�[���E�n�~���g���j�A��S���X�̍ȃW���f�B�X�̑o������a�܂�Ă���B
�@�������A������ނ��F���ɕ��˂������[�U�[��������A����I�F���l���X���X�����Ƃ������~��Ă����i��Ȕn���ȁj�B�F���l�̓T�[�t�B���̂��Ƃ��d���g�ɏ���Đ����琯�֓n������A����ΉF���̃o�b�N�p�b�J�[�݂����Ȑl�������i�����g�����j�B���`���[�h�͂�������F���l�ƒ��ǂ��Ȃ��đł������邪�A�W���f�B�X�͉F���l����g�p�Ɏ����Ă��铹��ɖڂ�����B����͂ǂ�Ȃ��̂��t���Ȃ��i�����炭�j����ł��j���G�̃V�[���h�������u�������B�����~�ɋ��ꂽ�ޏ��͂��������肵�悤�Ɗ�ނ̂����E�E�E
�@�V�[���h�ƌ����Ă��A�v���X�`�b�N���A�N�����̓����Ȕ��p���ƑO�Ɍ���邾���̈��オ��Ȃ��̂ł���B����ȃ����A�C�f�A����S�E�P���[�}���̔��^�̉��Z�������āA�㔼�́u�����������ɕ������͂������Ȃ��v�ƌ��������Ȃ�悤�ȋ��|�𖡂킹�Ă����B
�@���̍�i���D��Ă���̂́A�����̃V�[���h�ƁA�v�ƍȁA���Ƒ��q�A�l�ԂƉF���l�A�̊Ԃɂ���l�Ԃ̐S�̃V�[���h�Ƃ������ƃ����N���Ă��邱�Ƃł��낤�B�����͎��Ǝ����ƌ�������܂ł����A�v�������������������Ƃ��Ƃ�����̂ŁA��邹�Ȃ��v��������B
�@�r�{�́w�T�C�R�x�̃W���Z�t�E�X�e�t�@�[�m�B
|
| ��21�b |
�F���l�̗����q
�gThe Children of Spider County�h
�@�@�ēF���I�i���h�E�z�[��
�@�@�r�{�F�A���\�j�[�E���[�����X |
�@�����炱�̖M��l�^�o������B
�@�V�˓I�Ȋw�҂Ƃ��Ċe�E�̏d�v�ȃ|�X�g�ɏA���Ă����S�l�̎�҂��قړ����Ɏ��H����B�����̌��ʁA�Ȃ�Ƃ��̂S�l�͓������ɓ��N���������ɐ��܂�Ă邱�Ƃ������B���������e�͎��H���A�~�h���l�[���͑S���G���X�i������Ƃ₾�ȁj�B�c��������m�\�������A����ȍ˔\���������B���̃X�p�C�_�[���Ɏc���Ă���T�l�ڂ̒j�C�[�T���̑��݂�˂��~�߂��F���ǂ̃W�����͔ނɉ���Ƒ��ɕ������A�ނ͎E�l�e�^�ōS������Ă����B�����đ��̎��ӂł͓�̐l�����Ö�B
�@�������ǂ����ŕ��������Ƃ�����悤�Șb�ł���B�Ђ���Ƃ��āw�A�X�g�����c�x�̃��g�l�^���i�Ⴄ�j�H
�@����͂���Ƃ��āA���̂S�l�̓G���[�g�Ƃ��Đ������Ă�̂ɁA�����\�͂������Ă����͂̃C�W���△�����Ń_���ɂȂ��Ă��܂��l������Ƃ������\�V�r�A�Șb�ł����B�G���X���l�̉��l�ς��͂����肵�Ȃ��̂ŁA����Ƃ��Ă͍��ЂƂ̈�ہB�㔼�͗��l�Ƃ̓����s�ƁA�A�����J���E�j���[�V�l�}�݂����ȓW�J���Ȃ��Ȃ��B
|
| ��22�b |
�F���A��
�gSpecimen: Unknown�h
�@�@�ēF�W�F�����h�E�I�Y�����h
�@�@�r�{�F�X�e�B�[�����E���[�h |
�@�Z�J���h�V���[�Y����A�e�R����̂������A�F����ɂ����h��Șb�������Ȃ�B
�@�F�����痈���������������Ēn���S�̂���@�Ɋׂ�Ƃ����A���ł����o�C�I�n�U�[�h��`������i�B���Ԍn�̔j��Ƃ����e�[�}�ɂ��Ȃ葁�������ɒ��ڂ��Ă���B�܂�������̉F���D�Z�b�g��A�F����Ԃł̑D�O�����ȂǁA��|����ȃZ�b�g�������́B
�@�F���X�e�[�V�����ɂ������Ă����L�m�R�݂����ȕ���������������A�D���̎������ō͔|���Ă݂��Ƃ���A�Ԃ��炭�B���̉ԁA�P�{��������Ƃ����ɂ���蕨�����_�ŏ킹�邪�A��ʂɏo�Ă���ƕs�C�����B�Ƃ������悭����Ȃɍ�����ȁA�Ɠ��B�ǂ̋�J������������B
�@�������F���D�̏�g�����ǂ��l���Ă����������̐A�����u�������Ȃ��ŕ��u���Ă邵�A�����n���Ɏ����A�낤�Ƃ���̂����炠�܂�ɂ����d���B�n��̌R�������̖h�쏈�u���Ƃ炸�A���ʂ̊i�D�Ō���ɂ����Ⴄ���B�܂���͂肱�̎���A���̒��x�̊�@���������Ƃ������Ƃ��낤�B�n��̎i�ߊ��̌��f�͍��̊��o�Ȃ�Â��Ǝ���邩������Ȃ����A���\�ٔ�����B
�@�����������̓n�A�H�Ƃ��������B
|
| ��23�b |
�V���Փ˂̊�@
�gSecond Chance�h
�@�@�ēF�|�[���E�X�^�����[
�@�@�r�{�F�\�[�j���E���o�[�c |
�@�V���n�̉F���D�{�݂����̓��m�z���̉F���D�������A�Ƃ���������ƃW���[�E�_���e�����肪�D�������Ȑݒ�B�F���l�͗V���n���Œ�����݂��āA�����g�������悤�l������I���āA��D������B�����ɂ͂Ƃ�ł��Ȃ��ړI���������̂��i���ĖM�茩��Ε������ł����E�E�E�j�I
�@���\�����b���Ǝv���̂����A���ꂩ����Ď��ɘb���I���B�r�{���ǂ���u�M�����N�V�[�N�G�X�g�v�݂����Ȗʔ������̂ɂȂ����Ǝv���̂����E�E�E�Ƃ���������ȍr�����m�Ȑݒ�Ȃ�R���f�B�Ƃ��ĎB��ׂ��������B�\�Z���Ȃ��Ȃ��ė����̂ł��̒��x�ł�����������̂��낤���B
�@�������ĉF���D�K�C�h�̃o�C�g�����Ă��邵���Ȃ��j�i�h���E�S�[�h���j�������B
|
| ��24�b |
���ւ̖S��
�gMoonstone�h
�@�@�ēF���o�[�g�E�t���[���[
�@�@�r�{�F�W���Z�t�E�X�e�t�@�m |
�@���ʂ̃Z�b�g�A�F���l�̑��`�Ƃ��̐��E�ρA��l�����Ђ�����펞���̉Ѝ�������l�ԃh���}�A�Ȃǂ����܂��g�ݍ��킳���Č����̑�����i�B
�@�A�����J�̌��ʒT�������A�n������l�H���Ƃ����v���Ȃ����a�R�O�������炢�̋��̂�����B��n�Ɏ���������i����܂����̊u�����u���Ƃ�Ȃ���ȁB���d���I�j���A���͂��̋��̂̒��ɂ́E�E�E�I�F���l�������̂ł����A���ꂪ�n����̂ǂ̐����ɂ����Ă��Ȃ����I�ŕs�C���ȃf�U�C���B���̂����ۂ��Ȑ������l�Ԃ��猩��ΐ_�ɂ��������m���������Ă����Ƃ����̂��A�E�^�[���~�b�c�炵������B���������͂��̉F���l�ƗF�D����茋�Ԃ��A�ނ�͒n���Ō����ΖS���҂������E�E�E�B
�@�������Ȃɂ����A�E�^�[���~�b�c�炵���̂͌����̔s�k�����낤�B���_����䂦�u�l�Ԃ̑����v�u���S�̎��R�v�Ƃ����e�[�}����������ɂȂ�̂����B���̕č��������炱�̌����͂��肦�Ȃ��B
|
| ��25�b |
���̒n�������߂� |
�@�E�H�[�����E�I�[�c�ƌ����A�T���E�y�L���p�[�̉f��̏�A�A���ɒj�����f��w�K���V�A�̎�x�ł͎�����Ĉ�ې[�����A���̉������ł���������Ⴄ�Ƃ��܂��܂��B
�@�Ȃɂ���قƂ�ǂ̃V�[���œ������S�[�O�������đf�炪�����Ȃ��B�����ăS�[�O�������ƁE�E�E��͂�f��͌����Ȃ��i�j�B
�@���������˔\�̉e���Ń~���[�^���g�Ɖ������l�Ԃ̔ߌ����AW�E�I�[�c�͉��������Ă���ƌ����悤�B�l���D�ꂽ�\�͂�g�ɒ����Ă��^�����ǂ��납�A���܂Œ��̗ǂ���������������C���������A�a�O�����B�j�͒��\�͂��g���Č������Ƃ����悤�Ƃ���B�܂��܂����͂��甽�����A���\�͂ɂ��\�͂�����ɖ\�͂ނ̂������B���̒j������I�ɔ��邱�Ƃ͈�T�ɂ͂ł��Ȃ����낤�B
�@���������A�S�Ȑl�ԊW�̕�����A��̂Ȃ��f���ɂ����Ƃ��낪�܂����܂��B��ɃM���M���Ƃ�t���鑾�z������ɏő��������̂ł������B
|
| ��26�b |
��K�ɂ��鐶�� |
�@����ҁi���̃V���[�Y�ɂ͂��������l���悭�o�Ă���j�̃m�[�g���́A�Ђ��Ȃ��Ƃ���l�����ꂽ�ꏊ�ɂ���������ȑ�@��ɓ��荞��ł��܂��B�����ɂ͂��Ă̑受�D�A�V�v�w�A���K�����Ȕ������̂S�l�������B��Ȏ�荇�킹�̔ނ�͂܂��A�ԓx�����������������A���̗��R�͂������������B���̉��~�͈�x��������A��x�Əo���Ȃ������̂��I�����Ă��̉��~���ł͎��Ԃ��i�܂Ȃ����Ƃ�m��B�ނ�͐��\�N�Ԃ��̉��~�́u��K�̐����v�Ɏ���ꂽ�g�ł���A�ȗ��܂�����������Ă��Ȃ������B�����ăm�[�g�����܂���K�ɏ��������̂����E�E�E
�@���̃V���[�Y�̒��ł̓t�@���^�W�[�F�������A�����x������Ȃɍ����Ȃ����A������ۂɎc���Ă�����i�B���̗��R�͂����炭�A�u�O������u�₳�ꂽ��ԂŏI���Ȃ�������i����ƒm��Ȃ���j�J�肩�����l�X�v�u�قȂ鎞��Ԃ���j���̔ߗ��v�Ƃ������{�l�D�݁i�����ꕔ�ƌ�����������j�̐ݒ�ɖG�������炾�낤�B
�@���X�g�̌��i�����\�V���b�N�B
|
| ��27�b |
�F���̌��� |
�@�j�b�N�E�A�_���X�ƌ����A������B�f��œ��{�l�Ȃ�ΒN�����m���Ă���o�D�A���ɒj�����f��w�t�����P���V���^�C���Βn����b�x�ł͎�����Ĉ�ې[�����A���̍�i�ł͂����Ȃ��`���s�����ł��B�Ȃ�ƂȂ��j�R���X�E�P�C�W�Ɏ��Ă�B
�@�q����ł̃g���u���Ōx�@�ɒǂ���}�C�N�i�j�b�N�E�A�_���X�j�A�������A�p�[�g�̃h�A���J����Ƃ����͒n�����牽�����N���ꂽ�A���f�����������I�u����ł͂��ꂩ��F����ɎE������������Ă��������܂���v�A���f�����l�͉F������Q�̐��̐l�Ԃ�I�сA���̐킢�Ԃ���������Ė����ނƂ����A���[�}����̃O���f�B�G�[�^�[�݂����Ȃ��Ƃ���Ă����̂��B����̑ΐ�͒n����\�}�C�N�ƃ��[���i�i���V�[�E�}���[���jVS�J���R����\�i�قڃP�_���m�j�̂���l�A�������ق��̐��͖ŖS�B���ۂ����l�����A���ނ��Ă��n���͏��ł���ƌ����A�a�X�Əo�ꂷ��B�A���f�����l�̖��ɐa�m�I�ȕ����������������B�ΐ�ꏊ�̓A���f�����̉q���ŁA�n���̃W�����O���݂����ȂƂ���B�H���͎O�����A��ѓ���֎~�B
�@�t���h���b�N�E�u���E���̏����w���Z��x������Ƃ����L���ȍ�i�B���́u�s�𗝂Ȍ����v�Ƃ����p�^�[���́A���̌�F�X�ȃo���G�[�V�����ނ��ƂɂȂ�B���̐���ň�ې[���͉̂i�䍋�̃}���K�w�^�钆�̐�m�x���B
�@�킢��ʂ��āA�l���𓊂��Ă����}�C�N���S�̃g���E�}�ɗ����������������Ă����Ƃ����X�g�[���[�ł�����܂��B |
| ��28�b |
�F�����] |
�@�e�R����̂��߂ɃX�P�[�����傫���Ȃ����̂͂������A�X�g�[���[���喡�ɂȂ����͔̂ۂ߂Ȃ��B��͂肱�̍�i�̂悤�ɂ������ʂ̓��퐶���ɗ�����������A�����ւ̕s����`�������̂��A�E�^�[���~�b�c�̑�햡�ł��낤�B
�@�x���W���~�����͍ȂƑ��q�̒����R�l�Ƒ��ł������B���̉Ƃ̎����̃Z�b�g���傫���Ă�����Ƃт����肷��B���̉f��̂��̂𗬗p�����̂�������Ȃ����B�Q�K������̂ňꌬ�Ƃ��Ǝv������A��ŃA�p�[�g���ƕ�����B�ŁA�����Ƀ[�m�Ƃ����a�m���K�˂Ă���B�ނ͐��{�̋���v���O��������h�����ꂽ�ƒ닳�t�Ɩ����B�����̍��Ƃ�S���D�G�Ȏq�������𐭕{�����ڎw������E�E�E���_�Ȃ��Ƃɂ���̃P�j�[�N���I��܂����A�Ƃ����̂��B
�@�������Ė����K�₵�ăP�j�[�����炷��[�m�������A�x���W���~�����͂���s��������Ă��B������e���ُ�ɍ��x�ɂȂ��Ă���̂��B�����Ĕނ̓[�m���̋����̐��̂�m��̂������B
�@�n�������̂��߂Ɏq����_���A�Ƃ����̂́w�E���g���}���x�̃��t�B���X���l��A�z������B�[�m���������ۂ������A�����ɂ��a�m�I�Ȉ����A�Ƃ������͋C�B���̈���A�����ɂ��x����������������̃x���W���~�������A���q����邽�߂ɂ��̈����I�ȃ[�m���ƑΌ����悤����Ƃ��낪��������B�ǂ����Ă����Ȃ������Ȃ��̂����E�E�B�N���C�}�b�N�X�܂łقƂ�ǎ����̃V�[���Œn���ȓW�J�����A�Ō�̂ǂ�ł�Ԃ��ƂƂ��ɑ�|����ȓ�����ʂ�������B���w�A�����A�X���[���[�V�����Ǝ��Ă�Z�p���������Ƃ����������B
�@�d���ƂƂ��ɏo������[�m���̓��B�������������B�Ǎ�B
|
| ��29�b |
���~�m�X���l�̉A�d |
�@���钩�A�T�C�����i�T���E���i���[�J�[�j�͍ȁi�t�B���X�E���u�j�ɗ����b�������������Ă����B���͉ƒ�ɂƂ����ێ�I�ȕv�ɁA�W���[�i���X�g�ł���Ȃ͈��z�������̂��B�Ԃŏo�Γr��ŔY�݂�F�l�ɑł�������T�C�����B
�@��������ȉƒ�̂���������l���̋�Y�́A���͔ނ�ɂƂ��Ă��͂≽�̈Ӗ����Ȃ������̂������B��̂����ɔނ�̏Z�ފX�́A�܂邲�ƃ��~�m�X���ɓ]������Ă����̂��I���~�m�X���l�͒n���l��N������ɓ������āA�z��Ɏg���邩�ǂ����̃T���v���Ƃ��Ĕނ���q���C�Ƃ܂�ł݂������������B�n���ł͊X�̂������ꏊ�ɋ���ȃN���[�^�[���ł��Ă����B
�@�܂��ɕč��Łw�Y�������x�ł���B�O���ɐl�X�̓��킪���J�ɕ`����Ă���̂ŁA����炪�����Ƃ����Ԃɕ��Ă��܂����|���ǂ��o�Ă���B���������ʔ������Ȃ��߂��Ă�������A����ȓ��X�ł��炩�������̂Ȃ����̂ł��邱�Ƃ��v���m�炳���B�Ƃɂ����Â��b�ŁA��͂�Ԏ���Ĉꎞ�č��𗣂�Ă����T���E���i���[�J�[�i�ē����C�j�̎v��������̂��B�F���l��������镐����Ȃ���A�q�[���[�����Ȃ��B���͂Ȓ��������͍Ō�ɒn���N����j�~���邽�߂ɂ���s�����Ƃ�̂����A�܂Ȃ����Ă͌����Ȃ��B |
| ��30�b |
�唚�� |
�@���i�[�h�E�j���C���o�����Ă��邪�A�`���C���ň�ۂ͔����B�j���C�͌�̕��̘b�Ŋ��܂��B��l���͌��q�͌������̏����}�[�V�������m�i�W���[�W�E�}�N���f�B�j�Ƃ��̍ȃ��[�����i�V�O�j�E�n�b�\�j�B�r�{�̃��X���[�E�X�e�B�[�u���X�͑�P�Q�b�ɑ����āA��ɒ��މȊw�҂̖O���Ȃ��T�����_�ƕv�w����`���B
�@�F����������Ǝv�����V��̑f���q�������}�[�V�������m�́A��������q�F�ɕ����߂Ċώ@����̂����A���˔\���ُ�ɋ����Ȃ�A��ƈ��i�S���h�앞�j���]���r�̂悤�ɂȂ薽�߂������Ȃ��Ȃ�B��̑����̂����Ɗ�͂Ȃ��A�h�앞�̒���d���������Ă����B
�@�ǂ���炱�̗��q���ނ�𑀂��Ă���Ƃ����v���Ȃ��I�����Č��q�F�͖\�����n�߁A���̂܂܂ł̓����g�_�E���K���I�^���̉𖾂ɓ��]���i�锎�m�����E�E�E
�@���������ɋN����ٕςɑ��A�O���܂ŗ��_�ŗ����������n�[�hSF�B�U�O�N�ɔ������ꂽ����̃N�F�[�T�[�i���͂ȓd�g����o���Ă���P���ł����_�ł��Ȃ���̓V�́j�̘b���������Ă���B���˔\�ŃP���C�h�ɂȂ��ƈ���A�]���r��������ƈ��̌Q��̕|���A�㔼�̑唚���J�E���g�_�E���̃T�X�y���X�Ȃlj��o���͋�����������������B���ʂȂ���u���߂��I�킩���I�v�u���Ԃ�����Ȃ��I�v�ƌ��\��C�Ȕ��m�����B���鉜��������͂���B
�@�����������͂�����Ȃ�ł������߂��I |
| ��31�b |
�l�ԃJ�����I�� |
���̃J�����I���Ƃ����薼�ɂ͓�d�̈Ӗ�������B����̌v��̓��e���̂��̂ƁA���C�X�̂���܂ł̐l���Ƃł���B
�@����X�̒��ɉF���l�̏�����D���������Ă���B���炭�Ď����Ă����R�͔ނ炪���̖ړI�Ŕ��Ă����̂��l�������˂Ă����B�����ŏ��ǂ̐l�Ԃ���Ă���B�u�X�p�C����������܂��傤�B�K�������܂��B�v
�@���̒j���C�X�i���o�[�g�E�f���o���j�́A�ꖖ�̃��L�V�J������Ńx���x���Ɉ�����Ă����B�����Ɍ�납��E�ъ���Ă����j�������Ȃ�e��˂�����B�G���I�������C�X�̊�����s������ƁA�ڂɂ��~�܂�ʑ����ŏe���̂��A�����Ă����n�G�������̕��Œj���i�E�����I�@����ׂ��I���Ƀi�`�������E�{�[���E�L���[�I�E�l�@�B�I���̌�x�g�i���l�����i�p�[���ŏĂ������������̂��Ƃ͂���i�Ⴄ�f���j�B
�@�ŁA���̃X�p�C�Ƃ����̂��A�Ȃ�Ɛl�ԂɎ��Ă������Ȃ��F���l�ɕϐg���āA�F���D�ɐ�������Ƃ������́B�g�̂���`�q���x���ŕω������A�g���S���F���l�ɂȂ肫��Ƃ����̂��I���m�u���ł͐������Ă܂��B���v�A�I������猳�̑̂ɖ߂��܂��B�v�M�p�ł��ˁ`�B
�@�����������X�p�C�����ŐS���r���C�X�͂��̃~�b�V��������������B
�@�u�Ȃ������C�����邩�A�q�[���[��]�ł��`�����ł��Ȃ��B���̑��݂͔C���̓���ɉ߂��Ȃ��B�C�����Ȃ���Α��݂��Ȃ������R�A�C���̂��߂ɉ������Ƃ���������A���݂��Ȃ����̓}�V���B���ɂ͒N�����Ȃ��B������l���A�����Ă����l���E�E�E������ł��邱�Ƃ����A���ꂾ�����B�v
�@���o�[�g�E�f���o�������ӂȂ��ǓƂȒj�������Đ�i�B�J�E���^�[�E�J���`���[�A�قȂ镶���Ƃ̏Փ˂ƗZ�a�A�A�����J�Љ��̃h���b�v�A�E�g���v�킹��㔼�̓W�J�ȂǁA�A�����J���E�j���[�E�V�l�}�̖G�������B
|
| ��32�b |
���̑h���� |
�@�J�[�V���i���F���E�}�C���Y�j�ƃ��I�m�[���i�o�[�o���E���b�V���j�͕����������Ă��鈤�l�̃A���h�����ΔȂœŎE�A���̂��Ԃ̃g�����N�֓���Ďn�����悤�Ƃ��邪�A���I�m�[���͋��|�ɂ����ē����o���Ă��܂��B���J�̒��A��l���H�����͑傫�ȌÂ����~�A���ɂ͓�̎�ҁi�f�r�b�h�E�}�b�J�����j�Ƃ����ɂ��ӎU�L���Ӗڂ̘V�����B
�@��҂̓��I�m�[���ɟ�X�ƌ��A���͎��Ԃ�k���Ď��l���Ԃ点����@�������B��������Ő����Ԃ����E�E�E���I�m�[���͓�̕����Ɉē������������A����A�Ԃ̃g�����N�Ɏ��̂͂Ȃ������E�E�E
�@�O���͂܂�܃t�����X�f��w�����̂悤�ȏ��x�A�㔼�́w�T�C�R�x�E�E�E�Ƃ������W���Z�t�E�X�e�t�@�m���ĂЂ���Ƃ��āw�T�C�R�x�����̐l�Ȃ̂��H�����p�^�[���������B
�@�₽��J�������[�N�ɋÂ��Ă��ăz���[�T�X�y���X�Ƃ��Č���͊y�������A�ʂɁw�A�E�^�[���~�b�c�x�łȂ��Ă������悤�Șb�ł���B
|
| ��33�b |
�R�W���I���痈�����m |
�n���̃^�C���X���b�v
�@�r�p������n���ʂĂ��Ȃ������E���Ƃ������E�A���z�̌����˂����Ƃ͂Ȃ��B�E�l�����̌����Ԓf�Ȃ���ь��������B���E�͂Q�卑�Ƃɐ^����ɕ�����ĉʂĂ��Ȃ��푈�ɖ������Ă����B�F�߂����͂Ȃ����A���ꂪ�R�W���I�̒n���̎p���I�u�E�E�E���̕��m�̖��̓N�����A���܂ꂽ�����獑�ƂɌP������A�������������m��Ȃ��B�G���E�����Ƃ�����ړI�Ɉ�Ă�ꂽ�E�E�E�v�����A�ނ͐��ɐ키���߂����ɐ��܂�Ă����j�A���ɂ̐퓬�}�V�[���I���[�T���E�E�F�|���I
�@����Ȑݒ�͍��������ꂱ���|���Ď̂Ă�قǂ���킯�ł����A����͂��̐�삯�ł͂Ȃ����H����܂ł̃V���[�Y�̂��̂Ɣ�ׂċC�����̂́A��y�������܂��ēW�J���X�s�[�f�B�ɂȂ��Ă��邱�ƁA�ו��̂��������ł���B
�@�����̕��m�̓��[�}����̂悤�ȃR�X�`���[���Ȃ��A���̃w�����b�g����͐₦���u�E���A�E���A�E���E�E�E�v�ƌJ��Ԃ�������������B�u�i�ߕ��v���痬���Ă���炵�����A���]�̎�@�ł���B����ɂ͖h�����u���{����Ă��āA�]�v�ȉ��͕������Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���B�͂������Ɓi���̂�������������炩�Ԃ��Ă���̂Łj�ɓx�̕s���Ɋׂ�\�ꂾ���B�ނ͓����悤�Ȋi�D�������u�G�v�Ǝ���g�ݍ��������Ă�����Ƀ^�C���X���b�v�i�e�ׂ͏Ȃ��j�I�U�O�N��̃A�����J�̎s�X�ɍ��R�Ǝp�������B�����Ȃ�̓o��ɑ����o���s���B�����Ŕނ������Ă����e�𗐎˂�����w���E�̒��S�ň������������x���̂��̂Ȃ��A�����̊Ԃɂ���ȉf���𗬂��킯�ɂ������Ȃ��̂ŁA�p�g�J�[�P��n�����������Ōx���Ɏ�艟�������A�R�́u���_�ُ�Ҏ��e���v�ɑ��҂����B���̐��̕s���̒j�����邽�߂ɁA���ǂ��猾��w�҃P�[�K���i���C�h�E�m�[�����j���h�������B�R�l�ł��G�[�W�F���g�ł��Ȃ��A�����̐S���̂Ȃ����������ɂ̐퓬�}�V�[���ɑΛ�����킯�ł���B
�쐶�̏��N
�@�P�[�K���͔ނ̘b�����t���ɓx�ɂȂ܂����p��ł��邱�Ƃ�˂��~�߂�B���̓N�����i�}�C�P���E�A���T���j�Ƃ����炵���B�u�b���X�s�[�h�������A����𑽗p���Ă��܂��B�v����͎��ۂ����Ȃ��Ă܂��ˁB���̎���̉f��̉p��͎��ł��������邭�炢�����ƕ��@�ɑ����Ĉ���ꔭ�����Ă��܂����A�V�O�N�ォ�炾��X�����O�������Ȃ��āA�ŋ߂̃A�����J�f��̉p��͑S�R�������܂���B�A�N�V�����f�悾�Ƃ�������グ�ł��B�S�O�N�̊ԂɃA�����J�̉p��������ԕω����Ă���Ǝv���܂��B
�@�����Ă��郌�[�U�[�e�́u�o���o���ɕ����������A�������i�͂R�����Ȃ��B���i���ɂ��Ă������v�炵���B����͍\�����P���Ȃ̂ʼn��ɂ����J���V�j�R�t��A�z���܂��ˁB
�@�P�[�K���̓N�����ƃT�V�ŔS�苭�����炵�悤�Ƃ���B�G�������āu�����A�C�A�k�B�v�Ƃ������I�Ȍ��ꂩ��n�߂�B���ɂ͓{�肠���A����ꂽ�肷��B
�@�ŏ��A���\�������N�����͂������邤���ɂ���P�[�K���ɐS���J���Ă����B���̂悤�ɖ�b�̂悤�Ȑl�Ԃ��ꂩ�狳�炷��A�Ƃ����V�[��������Ǝ��R�ƐS���a��ł���̂͂Ȃ����낤�H�ߋ��̂���������ނ̉f��A�w�쐶�̏��N�x�w��Ղ̐l�x�w�J�X�p�[�E�n�E�U�[�̓�x�A�l�Ԃł͂Ȃ����w�z���C�g�E�h�b�O�x�Ȃǂ��v�������ԁB�v���Ɂu����v�Ƃ������̂̌����I�Ȋ�сA�̂悤�Ȃ��̂�ڂ̓�����ɂ��邩�炾�낤���B���{�ł͍��w�Z�Ƃ����ƁA�w�Z�ɍs�������Ȃ��l���}�����Ă���Ƃ��낭�Șb���Ȃ����A���E�̑啔�����߂�n�������ł͂ނ���܂Ƃ��ȋ���������Ƃ����Ȃ��q�������������ƕ����B�{������Ƃ������̂́u�����v�ł���A�m�邱�ƂƂ͊�тł���A�w��Ƃ����͖̂ʔ������̂ł���͂��Ȃ̂����A���ۂ͂������܂������Ă��Ȃ��B
�^�[�~�l�[�^�[
�@���ς�炸��ȂȃN���������A�u���O�͓G����Ȃ��B�v�ƌ����A�w�����b�g�Ȃ��ł����Âł�����悤�ɂȂ����̂ŁA�P�[�K���͔ނ������̉Ɓi�ȁA��j�ꏗ�j�Ƀz�[���X�e�B�����悤�Ǝv�����i���d���I�j�B�Ƃ��Ƃ�����֏����Ă��܂����̂����A�Ƒ����o�ŏo�}����ꂽ�N�����́A�����[����Ƃ�ł��Ȃ��s��������i����̓l�^�o���ɂȂ肻���Ȃ̂ŋL�q�͍T���邪�A�ς��甚�ΕK���j�B
�@�ŁA���w���̖��ƒj�̎q�Ƃ��Ȃ�Ƃ����܂�����Ă����̂����A���������V�[�������Ă���ƃ����C�N����Ƃ�����A�N�������͑̊i�Ƃ����A��R�Ƃ����\��Ƃ����A���̗��Ɋ_�Ԍ�����D�����Ƃ����A��͂�V�������c�F�l�b�K�[���K�����낤�ȂƎv���B�W�F�[���X�E�L�������������̍�i�ɋ��������ꂽ�̂��������Ȃ��B
�@�܂��A�P�[�K���͔ނƂ̑Θb����R�W���I�̋���ׂ�������m��B�����̃A�����J�͖k���N�݂����ȑS�̎�`���Ƃɐ���ʂāA���m�͐l�H�q�{�Ŏ��X�Ɂu���Y�v�����B�N�����������������e��m��Ȃ��l�Ԃ������B���߂��S�Ăł���A�l�i�͔ے肳��Ă����B
�@����ȃh�^�o�^������Ă邤���ɁA�ʂ̏ꏊ�ł͗�́u�G�v���^�C���X���b�v���Ă����B�ނ͒T�m�@�Ŏ����̑����T���Ă��܂���Ă����̂����A���ɃN������T�m�����I�N�����̕��͂��̐��E�ɂ�����������Ŋ����Ȃ܂��Ă��ċC�����Ȃ��B���₤���I�P�[�K����ƁI
�@�ƁA���̃n���E�b�h�f�悾�����炱�����炪������Ȃ�ł����A���̃m���ł��̌�����Ă��܂��ƌ���������H����Ă��܂��܂��B���ۍ��������炱��܂ł̓W�J�̓T�����ł����Ȃ����낤�B���������B�̔��B���Ă��Ȃ����������A��͂�SF�ƌ����ǂ��h���}�d���ł���A���Ƃ͎��_���܂���������Ă����Ƃ����ׂ��ł���B
�@�W�F�[���X�E�L���������ḗw�^�[�~�l�[�^�[�x���o�ꂵ���Ƃ��A�G���X���́u���̃p�N�����낪�I�v�ƃL�������������i�i���Ɍ����u�^�[�~�l�[�^�[�ٔ��v�j�B��Ɂw�^�[�~�l�[�^�[�x�̃N���W�b�g�Ɍ���Ƃ��Ă��̍�i�Ƒ�R�V�b�w�K���X�̎�����j�x�i����������j��t�������邱�ƂŘa�������B
|

VOL.�R |
| ��34�b |
�F���ɎU���������� |
�@���̖M��Ȃ�Ƃ��Ȃ�E�E�E�B�w�����z���F���x���݂Ɋ�ȑ薼�ł���B����́wCold�@Hands�AWarm�@Heart�x�Ƃ����������������́B
�@�����T���ɍs���Ă�����s�m�W�F�t�i�E�B���A���E�V���g�i�[�j�͋����l�ɂƂ����A�����������R���Ă����B���̎��ÂƉF���l�ގU�ɍȁi�W�F�����f�B���E�u���b�N�X�j�����g�I�ȃT�|�[�g������Ƃ����A�u�A�E�^�[�E���~�b�c�v�ɂ͈ӊO�Ƃ悭����v�w�����́B���̖ѐU�藐�����ςȃ}�y�b�g�̉F���l���L���Ȃ̂����A�b�͂���܂�ʔ����Ȃ��B�ʔ����̂̓V���g�i�[�̉��Z�B�ݒ�͉ĂȂ̂����A�����l�Ɏ��t���ꂽ�ނ͑̉����������Ă����B����ōŏ��͏㒅���H�D�邭�炢�Ŗڗ����Ȃ��̂����A�V�[�����ς�邽�тɕ����������ɂȂ��Ă����B�ŏI�I�ɂ݂͂�Ȕ����Ȃ̂ɁA����������ɂ֍s���悤�Ȗh����Ŋ��S�����B�����Ƃ��Ă���悤�ȉ��o�ł͂Ȃ��̂����A����B�V���g�i�[���[���Ȋ炵�ĉ��Z����̂łȂ�����ł���B�܂������Ȃ�O�ɕ��ʂ͎���ł�Ǝv���܂��B
�@�E�B���A���E�V���g�i�[�͂��������p���m�C�A�I�ȉ��Z�����\�������B�悭����ƃC������Ă�悤�Ȗڂ��Ȃ�ˁB����䂦���A�w�X�^�[�E�g���b�N�x�ł������Ė͔͓I�ȑD���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�X�|�b�N�̂悤�ȗ�Âȕ⍲�����K�v�������B���o�[�g�E���C�Y�ē͉f��Łw�X�^�[�E�g���b�N�x�ŃJ�[�N�D�����A�䓪������̉��E�����Ƃ���C���ȏ�i�Ɏd���ďグ���B
|
| ��35�b |
�������菓��� |
�@�u菓��ҁv�́u�`���j���E�V���v�Ɠǂނ炵���B����̓V���[�Y�ł͒���������₩�Șb�B�يE�̒m���̂Ƃ̗F���`�������̂ł���B
�@�X�g�[�����w���m�́A覐������������Y���������K�l�������Ă݂��Ƃ���A�����ɂ���͂��̂Ȃ����m�����Ă��܂��i�w�[�C���u�x���H�j�B����͓��̐��E���痈�������������B���K�l�������������Ō��t���ʂ���Ƃ����s���̂悳�͂��Ēu���Ƃ��āA���̐����̑��`�A���z���ǂ��B���̐�����������݂��[���A�]���ĉ�����Ȃ�ǂ�ȕǂ����蔲���Ă��܂��Ƃ��������͐��������ǂ���������ʔ����B
�@��펯�Ȍ����̐₦�Ȃ��ϐl�̃X�g�[���ƁA�펯�l�Ŗʔ��݂̂Ȃ����i�̌Z�A�����Ȋw�҂����ΏƓI�Ȑ��i�̌Z��B�X�g�[���͐����ƒ��ǂ��Ȃ蓽�����A�Z�͖��m�̂��̂͊댯������r�ł��ׂ��I�ƍl����B�펯�ōl����ΌZ�̂ق����������Ǝv�����A���̍�i�͓O�ꂵ�Ă��̌Z�������`���A�����ɃV���p�V�[��������X�g�[���������l�ɕ`���B���̕Ό��Ԃ肪������B�܂��X�g�[���̔鏑�̃G���U�x�X���������W���A���E�t���[�}���́w���{�\�ƌ�����x�Ƃ��L�����m��傾�����悤�����A�Ȃ��Ȃ��̔��l�B�ϐl�ɗ����̂�������E�E�E�I�^�N�̖��ł��낤�B
|
| ��36�b |
�E���g���l�� |
�@�u�E���g���}���v�ł͂Ȃ��u�E���g���l�ԁv�E�E�E�܂�������ł����B������璴�l�ɕϐg���\�����n�߂�A�Ƃ��������̒P���Șb�Ȃ�ł��ȁB�����������Œ��ڂ��ׂ��́A���̖�CE�i�ӎ��g��j�����������炳�܂Ƀh���b�O�A���Ƀ}���t�@�i��A�z�����邱�Ƃł���B�P�X�U�U�N�A�܂��č��ł͍L�͂Ȗ����͌��݉����Ă��Ȃ��Ǝv�����A���ʉ��ł͍L�����Ă������Ƃ��v�킹��B
�@CE�����̈�l�A���m�n�̃A�J�_�搶�͜����Ƃ��Č����u�E�E�E�����������o�Ƃ͉����A��X������ڂɂ��镨�ƒm�o���g�債�Č����镨�A�ǂ��炪�{���Ȃ̂��Ƃ������Ƃł��B�ȒP�ȗ�ł��b���܂��傤�B�̗t�������Ă����Ƃ��܂��BCE�����҂ɂ͂�����t�̓�����������B�ߋ����������ł��B�킩��肪����o���A���ꂪ�������Ă����͂�ʂĂ�܂ł��ڂɉf���ł��E�E�E�v
�@�܂��u�_�������v�ƌ����l������炵���ł�����A�����������o�������l�����邩������܂���ˁBCE�̔��z�́A���_�͂ɂ���ē��̂��ϗe����Ƃ������Ƃ��炭��B��̃N���[�l���o�[�O�f��̓��̕ϗe����肵�Ă���悤�ŋ����[���B�ł���͂�N�X���Œ��l��ڎw���̂͂�߂܂��傤�B |
| ��37�b |
�K���X�̎�����j |
�@�n�[�����E�G���X���r�{�A�o�C�����E�n�X�L���ēA���o�[�g�E�J���v�o���Ƃ����h���[���E�`�[���ɂ��n�[�hSF�A�N�V�����B�ō�����ƌ����ƈ٘_�����邩������Ȃ����w�E���g���Z�u���x�ɂ�����w��l�f���̈����x�ɑ�������V���[�Y�������Ƃ���s�I���X�^�C���b�V���ȍ�i�ł��邱�Ƃ͊m���B�B�e�̃P�l�X�E�s�[�`��B�����̂悤�����A�����ł͈Â������������f�����������A���y�������̂Ƃ͕ς���āA���J���ȃW���Y�s�A�m�݂����ȉ��y��S�҂ɓn���Ďg�p���Ă���B
�@�u�g�[�^���E���R�[���v
�@�j�i���o�[�g�E�J���v�j����̊X�����܂���Ă���B�ނ͒ǂ��Ă����B���������҂Ȃ̂��A���̑_���Ă���̂��A�����v���o���Ȃ��B
�@�u�N�������̋L���������A�����E�����Ƃ��Ă���B�Ȃ����A���O�͒N���B�v����������܂Ŕނ͐��X�̓�ǂ����z���Ă����B�u�����Ă킪�e��f����Ȃ��ׂ����Ƃ���������B�v�ނ̍���=�u�K���X�̎�v�͍����\�R���s���[�^�[���ڂ̋`��ł������B��܂��O���ƃK���X�H�̎肪�����B���̎�͐l�����w�A���w�A��w�������Ă����B
�@�K���X�̎�ɖ₤�B�u�N����������ׂ����Ƃ����A���̒ʂ肾�BA�E�ǐՎ҂����Ă��鉩���̃��_����D�����ƁBB�E��x��2���̎��ԗ��s���\�ɂ���^�C���~���[������B�����j�邱�ƁBC�E�Ƃɂ������������邱�ƁB���́e��f���C�����邱�Ƃ��BD�E�e�w�f���S�������ΌN����������B�v
�@�������Ĕނ͂킯��������ʂ����ɍs���ɏo�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B�L�������������Ƃ͂����A�ނ̐g�̂��Ȃ��͓���P�����ꂽ�҂̂��ꂾ�����B�ǐՎ҂�ߊl����ƁA�V���Ȏ��������������B
�@�ނ̖��̓g�����g�B�ǂ���̓J�C�o�����l�A�ނ�̓g�����g�́e��f��_���Ă����B���łɎw�R�{�̓J�C�o�����l�̏����ɂ������B�u���ɕ�����̂́A�N�������̒n���ɐ�����Ō�̐l�Ԃ��Ƃ������Ƃ��B�v�܂��A�J�C�o�����l����Ԃ牺���Ă��鉩���̃��_���́A���Ԏ�����ł���A�g�����g���܂��牺���Ă����B����������ƁA�u���Ɍ����������Ɉ����߂���Ă��܂��B�u�^�C���~���[�͂ǂ����H�v�u���ƒn��̃f�B�N�\���E�r�����B�v���ꂾ�������ƃg�����g�̓��_�����������������B���l�̓p���Ə������B
�@�u�Q�[���v
�@������P�O�O�O�N��A�J�C�o�����l���P�����l�ނ͂P�����Ő������ꂽ�B�������ɂ��ĂV�O�O���l�̐l�ނ͍��R�Ǝp���������B�����ĔށA�g�����g������l���c���ꂽ�̂��B�l�ނ̍s����m��u�K���X�̎�v�������āB1000�N�O�̉ߋ��ɓ����Ă����g�����g��ǂ��āA�l�ނ̍s����T��J�C�o�����l�������܂����̐��E�ւ���Ă����̂��B�u�N�͐l�ލŌ�̊�]�E�E�E�����e��f�̓J�C�o���l�ɕ��i��D���v�Z�\�͂��s�\�����B�D��ꂽ�e3�{�̎w�f�����Ԃ��A�J�C�o���l�̈Ӑ}��T��B�Ȃ��N�������P�O�O�O�N��̒n���Ɏc�����̂��A���̗��R��T��B�v
�@�����ċ���Ȕp�Ђ̂悤�ȁu�f�B�N�\���E�r���v�ւ���ė����B���������㩂������I�u�悤�����g�����g�N�A���ꓯ�҂��Ă�����B�v�r���̎��͂ɂ͂��łɃo���A�[�������Ă��Ă��͂�܂̑l�B�������g�����g�͑O�ɐi�܂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�P�O�O�O�N��̐l�ނ��~�����߂ɁB�����Ď����͉��҂Ȃ̂���m�邽�߂ɁE�E�E�B
�@�`���ł��̕���̂��V���Ă����ׂďo�����B�g�����g�͂R�{�̎w���Q�b�g���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u�����ꂽ�r���̒��ŁA�����͂����鑊���|���A�w��D���B���̂��тɐV�������ɓ���A�\�͂����シ��B�����čŌ�̎w�͍ŏ�K�ɂ���G�̖{���n�ɂ���A�w��D������Ɂu�^�C���~���[�v��j��u������v���B
�@�͂����茾���Ă���̓Q�[���ł���B�U�U�N�̒i�K�ł��ꂾ���Q�[�����̍����f��Ƃ����̂͊B���Ȃ�̐�i���ł���B�Q�[�����Ƃ����A���_���̔��z���ʔ����B���ԗ��s�͎��R�̐ۗ��ɔ����Ă���̂ŁA���R�͉ߋ��ɖ߂����l�Ԃ�₦�����̎��Ԃɖ߂����Ƃ���B���傤�ǃo���W�[�W�����v�̃S���݂����Ȃ��̂ł���B����������~�߂�u�d���v�����_���Ȃ̂��B������Ƃ���ƁA�A���ƌ����Ԃɖ����Ɉ����߂���Ă��܂��B����͋��ʂ������_���B����������ȑ厖�Ȃ��̂��Ȃ�ň����������Ă��������ƌ�������Ɏ�Ԃ牺���Ă���̂��H�Ɠ˂����܂ꂽ��A�Q�[��������A�Ƃ��������悤���Ȃ��i�j�B�g�����g��������Ԃ牺���Ă���킯�ŁA�������X�N��w�����Ă���킯������t�F�A�ł���Ƃ͌�����B
�@�u�u���[�h�E�����i�[�v
�@���̕���͑S�҃r���̒��œW�J�����B���̃r���̈ӏ������āA�ǂ����Ō������Ƃ�����悤�ȁE�E�E�Ǝv���l�������낤�B�Â��A�o���b�N�����A�[���f�R�������ʂ����Ȃ��悤�ȃS�e�S�e�Ƃ��������ߏ�Ƃ�����������B����Ȑ��������A�e���X����˂��o������ۓI�ȃG���x�[�^�[�E�E�E���͂���͂��́w�u���[�h�E�����i�[�x�Ńn���\���E�t�H�[�h�ƃ��g�K�[�E�n�E�A�[���������J��L�����ꏊ�Ɠ����Ƃ��끁�u�u���b�h�x���[�E�r���v�Ń��P���Ă���̂��B���̌����̓��T���[���X�ɂ���A�P�W�X�T�N�z�Ƃ������ɌÂ����̂ŁA���݂ł������Ŏg�p����Ă���B�����w�u�������x�w�ł̊ό��q�����₽�Ȃ��Ƃ����B���ہA�g�����g�ƃJ�C�o���l�Ƃ̐킢�Ԃ�́w�u�������x��f�i������B�G���x�[�^�[�����ʓI�Ɏg���Ă��邵�A�����Ɖ������������łĂ���i�u�u�������v�ł͔��������Ă������A������̓}�l�L���̌Q��B�X�^�����[�E�L���[�u���b�N�́w����㩁x���H�j�B������O�̕ǂɂւ���V�[��������i�����ɂ͊X�̃l�I�����E�E�E�J�͍~���Ă��Ȃ����j�B�n�[�����E�G���X���͂��̍�i���Ȃ��āA�W�F�[���X�E�L����������i�����̂����A�n�[�h�{�C���h�ȃe�C�X�g�ƌ����A�S�̂̈�ۂ͖��炩�Ɂw�u���[�h�E�����i�[�x�ł���A�ނ̓��h���[�E�X�R�b�g���i����ׂ�����Ȃ��̂��H�܂��ʂɗ]�v�Ȃ����b�ł����B
�@�ŁA���܂��ܓ����x�ꂽ���K�̏��i�A�[�����E�}�[�e���j�ƈꏏ�ɑ���������ꂽ��A���삳�ꂽ�肵�Ă��邤���ɗ����萶������A�w�������Ă����o���ɂ�������^���Ȃ��ăC���C����������ƁA�����Ō�܂ň��������������B�u�Ȃ�قǁA����͕��������B���Ⴀ�����͂ǂ��ɂ���H�v�u����͂�����{�w���Ȃ��ƕ�����Ȃ��B�v����Ȓ��q�E�E�E(-_-;)
�@�����āu������v�ɂȂ������A�z�����ɂ��Ȃ������Ռ��̌������K���̂ł������B���̌����͌���ł��ʗp�����Ȃ����ȁB�͂����茾���āA���܂��I�Ƃ��������悤���Ȃ��B�����ă��X�g�V�[���ɂ́A���̃A�����J��y�f�悪�����Ă��܂����u�Â��v�u�ꂳ�v������B
|
| ��38�b |
���ق̋��� |
�@�A���f�B�i�G�f�B�E�A���o�[�g�j�ƃJ�����i�W���[���E�n���H�b�N�j�v�w�́A�������̍r��ŗ����������Ă��܂����̂����A�����łƂ�ł��Ȃ��ٕςɏo���킵�Ă��܂��B�͂ꑐ���P���Ă���̂��I�͂ꑐ���āA�悭�������ŁA���ɂ̂��ăR���R���Ɠ���]�����Ă��鋅��̌͂ꑐ�̂����܂���ďo�Ă��邶��Ȃ��ł����B���ꂪ�l���P������B�����Ĉꌬ�Ƃ̔_�ƂɘU�邷�邱�ƂɂȂ�B������͂ꑐ�Ɏ��͂܂�āE�E�E���ɂ͋��낵���Ȍ͂ꑐ�̉e���I�ߖ��グ�鉜����B���������Ɣn���݂��������A���Ẵ��C�X�E�V���[�{�m�[�͑�X�b�ł��A�ŏ��͔n���n�������ݒ�ōŌ�ɂȂ��ă]���Ƃ�����b����Ă���̂ŁA���Ȃǂ�Ȃ��B
�@�Ȃ����D��E�E�A���o�[�g���o������̂��A��ɂȂ�قǕ������Ă���B�͗ʂ̂Ȃ��o�D��������A�͂ꑐ�Ɗi������G�ȂƂĂ������͂��o���Ȃ��B�����ďP���Ă�����̂͌͂ꑐ�����ł͂Ȃ��Ȃ�B�J�G���̌Q��A��̏P���ƃp�j�b�N�f��̗l���ƂȂ�E�E�E�����Ă���ς�Ō�̓z���[���B
�@�A���f�B�͂���͓��̂������Ȃ��F�������́i�A���m�����l���H�j�����m�ɜ߈˂��Ă���Ɛ������A����ƌ�M����Ă��l���邾���E�E�E�B�N���C�}�b�N�X�ŁA��͂�E�E�A���o�[�g�͔[���̂��������������Ă����i�Ƃ��������̘b�͔ނ̃M�����ȊO�A���̂������Ă��鏊����������Ȃ��j�B
|
| ��39�b |
�ΐ��I���̋���ׂ��G |
�@�v�X�ɉF����ɂ�����|����ȍ�i�B�ΐ��́u���̊C�v�Ƃ������z���f���炵���B�悭����ȃZ�b�g��g�ȁB
�@�L�l�ΐ�������ꍆM1���͒�����A�����̂��ɏP�������������B�R�N��A�����b�g�i�A�_���E�E�F�X�g���o�b�g�}���̐l�j������D���Ƃ���M2�������i�����B�ΐ��ɂ�M1���̎c�[���������B�T�d�ɒ�����i�߂郁���b�g������s�����A�����ڂɂ��čŏ��̋]���҂��I���̍��Ղ��c�����l�Ԃ��P������́u��������G�v�Ƃ��������悤���Ȃ������B�����ĕ����̃o�b�N���[��т͎~�߂�̂��������A���̂�˂��~�߂悤�Ƃ��邪�E�E�E�H
�@������w�тꂾ�����o�ăY�Y�[���Ɠːi����l���܂������W���[�Y�݂����B����ɃJ�j�̂悤�ȋ���ȃn�T�~���Y�I�I�[���ƍ�����o�Ă���ȂǁA�r�W���A���I�Ɉ����B���̉��łǂ�����ē������Ă��邩�z������Ɗy�����B�������������������ł͉��ɍ��������Ă��܂��A������̂�����ɂȂ�Ǝv���̂����A���������Ȃ��H�v�����Ă���̂��낤���B
�@�{��͓N�w�╶���ւ̌x���Ƃ������e�[�}�͓��ɂȂ��āA���b��@���ɍU�����邩�Ƃ�����_�ɍi����������₷����i�ŁA����䂦���b�̑��`�͔O�������Ă���B
�@�Ȃ�ł�����A�r�{�̃W�F���[�E�\�E���́w�t�����P���V���^�C���Βn����b�o���S���x�̊��ɂ��Q�����Ă��������ł��B
|
| ��40�b |
��̘f���E���t�R�T�X |
�@�͂����茾���Ă��̍�i�̔��z�͂������B��������搶���A����̒r�̐^�̓��ʼnF���������i�����Ă����w�F�����x�Ƃ����Z�҂�`�������A���ꂪ���g�l�^�ł͂Ȃ����i�����͂�����̂ق����[���ł���j�B�l�^�s���̃n���E�b�h�f��́A���낻�낱�̘b�ɒ��ڂ��邩�����B�Ƃ������A�w�t�F�b�Z���f���̉F���x�Ȃ��B
�@�W���N���ꂽ�f���E���t�R�T�X���ϑ����邽�߂ɁA�W���i�T�����m�i�p�g���b�N�E�I�j�[���j�͌��������ɂ��̃E���t�R�T�X�̃~�j�`���A�����B�u�����������ɒ��a�Qm���炢�̔������ݒu����Ă���B�ϑ��f�[�^�Ɋ�Â��đ�C�A���x�A�n���A���x�A�d�́i�ǂ�����āH�j�A���z�i����̓��C�g�j�E�E�E�S�Ă𐳊m�ɍČ������B���̎����̊�ڂ́A���̊���DNA�𓊓����ĉʂ����Đ������a������̂��H�Ƃ������ƂȂ̂����A�����͐����A�~�j�`���A�̘f���̏�ɐA��������Ă����B�f���̕\�ʂ��������Ŋϑ�����ƒn�\��ʂ��X�тŕ����Ă����̂�������B���Ȃ݂Ƀ~�j�`���A�f���ł͏k�ڂ͂Q�O�����̈�i�]���Č������Ŋϑ����Ȃ��ƌ����Ȃ��j�A�n���̂P�b�łP�P�������o�߂���B�܂������������Ői�����i��ł���̂ł���B
�@���̃V�~�����[�V��������Ɍ�����i�߂�A����E���t���J���̏������e�ՂƂȂ�B���m�͓��Ӗ��ʂ��������E�E�E�B�قǂȂ����āA���������O�ňٕς��N����B���͂̐A�����͂�n�߁A���������o�^�o�^�Ǝ��Ɏn�߂�B���̈���A�f���̐����͏����ɐi�����Ă����B���łɋ����̎���ɓ����Ă����B���m�͒n���̐i���Ƃ��܂�ɂ����ʂ��Ă��邱�Ƃɋ�������B�����āA���������Ɋ���ȗH��̂悤�Ȃ��̂��o�v����悤�ɂȂ�B���̂�����u�E���t�R�T�X�S�[�X�g�v�͉e�G�Ō����Ƃ���́u���v�ɗ����g��ɂʂ�����݂�킹���A�͂����茾���Ĉ����ȃV�����m�Ȃ̂����A�����I�Ȑ��̓������ł���̂����݂��B
�@�f����̐������i������قǁA�S�[�X�g�͋���ƂȂ�A�������͎���ł����B����������X�̐��E���琶�C���z������Ă��邩�̂悤�ɁB���|�����������m�͍Ȃ�������ǂ������A��l�ߑs�Ȋo��Řf���ɑΛ����āA����s���������B�f����ł͐l�ނ��o�ꂵ�A�����̐l�ނ̗��j���Č����Ă����B�u�����̍����A�f���͒n���ɒǂ����Q�O���I�ɓ���܂��B���̌�́E�E�E�f����ʂ��A�����̒n����ڂɂ���ł��傤�B�����Ă���E�E�E�v
�@�Ȃ�Ƃ����낵���b�����A���ꂾ�����������Ă����Č����͌��\���ӂ��Ȋ����Ő�����������ł���B�����������A���������������\���Ƃ�����A������̉\�����l���˂Ȃ�Ȃ����낤�B��X���Z��ł��邱�̐��E���Ђ���Ƃ��ĒP�Ȃ�����ɉ߂����A�ォ�猰�����Ŋώ@����Ă��鑶�݂Ȃ̂ł͂Ȃ����H�Ƃ������Ƃł���B�E�E�E�܂��ϑz�ł����ǂˁB |
| ��41�b |
���{�b�g�@��ɗ��� |
�@�A�����J�̒n���s�s�i�Z���g���C�X�炵���j�̍x�O�A�����N�H�w���m�͌��������Ŏ�̍���܂��Ď���ł����B�����ɋ����킹�Ă������m��������l�Ԍ^���{�b�g�A�u�A�_���v�����m�E�Q�̗e�^�ŘA�s�����B�A�_���͊w�K���A�����I�ɘb�����Ƃ��ł��A����炠�����B�O���͋��������A�قڐl�Ԃɋ߂������B���m�̖Ẫj�[�i�A�V���L�҂̃G���X�i���i�[�h�E�j���C�j�̓A�_���̙l�߂�i���邪�A�x�@�͔p�����������s���悤�Ƃ���B�����ŃG���X�͗F�l�ŁA���Ă̓X�S�r�ٌ�m�����������͂�������l�Ԍ����ɂȂ�B�ِ����𑗂��Ă����^�[�}���E�J�g���[�i�n���[�h�E�_�E�V�����@�j�ɗ��ݍ���Ŗ@��ł��̖��Ɍ��������悤�Ƃ���B
�@����H�ED�E�V�����@�������B�������肵���̊i�A�_�a�ł͂��邪�A����܂ł̋�J���ɂ��܂�����ᰁA�����p�C�v���藣�����A�@��ł��|�P�b�g�Ɏ��˂�����ŕ����A���ЂȂǕ��Ƃ����Ȃ��p���A�����ɂ��_�����Â������ݕ������V���Ȑa�m�ł���B���̍��܂ł͂������������̖��̂���o�D�����\���āA�e����߂Ă����̂������͂Ƃ�ƌ�������Ȃ��B�����Č����V���[���E�R�l���[���H����A������ƈႤ�ȁB
�@�ނ͐Ԏ��i�܂����I�j�Ńu���b�N���X�g�ɏ���Ďd���������ꂽ���Ƃ�����̂ŁA����̖��ǂ���͔ނ̐l���ƃV���N�����Ă���̂��낤�B
�@�܂��A���i�[�h�E�j���C�́A�m�I�ŕΌ��̂Ȃ��A����ł��Ď����̐V���̔��荞�݂��ӂ�Ȃ�����I�Ŗ��N�Ȏ���������Ă���B
�@�J�g���[�̖ʒk����A�A�_�������͂ł͂��邪�A�l�Ɋ�Q�������Ȃ��D�������i�ł��邱�Ƃ�m��B�ނ̓A�_���̏،����炱��͎��̂��I�Ɗm�M���邪�A���{�b�g�ɕΌ������ؐl�̏،��̓A�_���ɕs���Ȃ��Ƃ���B���������̉��͂����͂��狰�����B�J�g���[�͌njR�������邪�E�E�E�B���̕ӂ̓W�J�́w�A���o�}����x��A�z������B���ۂ��̘b�����l���ʂ����~���ɂ��Ă���͖̂��炩���낤�B
�@���ہA���̍�i�̖@��V�[���͖{�i�I�i�퍐�����{�b�g�ł��邱�ƈȊO�j�ŁA����@���p����|���|����яo���B�������x���E�u���f�B�́w�y���[�E���C�X���x���肪���Ă��邾���̂��Ƃ͂���i����܂茩�ĂȂ��������j�B
�@��ʂɃL���X�g�����ł͐l�^���{�b�g�͌h������Ă���A�ƌ�����B�l�Ԃ��_�Ɏ����č��ꂽ�ȏ�A�l���l�Ɏ����č�邱�Ƃ͋�����Ȃ��E�E�E�B�S�[�����A�t�����P���V���^�C���̉����A���m�̐l���l�Ԃ͊F�A�����̏��Ƃ��A�ߌ��ɏI���B�ǂꂾ���M�ߐ������邩������Ȃ����A���{�b�g�J���ɂ�������{�̐l�^���{�b�g�̂������悤������Ƃ������ȂƂ��v���B���̍�i�ł��A�A�_���͒a��������Ɛ��w��o����̋Ǝ҂��爫���ł��݂�悤�ȖڂŌ�����B���̂悤�ȏ@���I�ȕΌ��������ɂ���Ă���Ƃ�����A�����Ƃ��Ă͗E�C�̂��邱�Ƃ������낤�B
|
| ��42�b |
���m��ʉF���̑����l�i�O�j |
�@�V���[�Y���B��̑O��2���\���B�����ăV���[�Y���ő�̖���B����A����������͂���Ȃ���͂Ȃ������͂��Ȃ̂����E�E�E�����炭��������A�n��g�ŕ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B�������Ȃ��猆��ł��邱�Ƃ͊m���B
�@�A�����J�͓���A�W�A�̖^���Ő푈�ɖ������Ă����i�x�g�i���Ȃ��ǁj�B�퓬���A�G�̏e�����A�����ɒe��������ՓI�ɏ����������m���������łS�l�����B�~���Y���сi�X�e�B�[�u�E�C���n�b�g�j�A�W�F�[���X�E�R�m���@�[�R���i�A�C���@���E�f�B�N�\���j�A�t�����V�X�E�n�h���[�㓙���i�f�B�[�E�|���b�N�j�A���o�[�g�E���i���h���i�W�F�[���X�E�t���[���[�j�̂S�l�ł���B���̂S�l�͎�p���ɁA�Q��ނ̔]�g���o��Ƃ����ٕς��N�����Ă����B�Ȋw��b�����鏑�A�_���E�o���[�h�i���o�[�g�E�f���o���j�͂��̂S�l�ɏo�������]�g�����ׂē���̂��̂ł��邱�Ƃ�˂��~�߂�B�܂肠���̈ӎv���S�l���܂Ƃ߂Ă���Ƃ������Ƃ��B�������ُ͈�ɑ����A�S�l��IQ�͂Q�O�O�ȏ�ɏ㏸�A���������̂��Ƃ��������Ă��錻�݁A���������Ȃ��~���Y���т������ĉ��̂悤�Ɏ��H���Ă����I���҂����S�l�𑀂�A�Ȃɂ��r�Q���Ȃ����Ƃ����ł���E�E�E���Ԃ��d�������o���[�h�͂��������s�����J�n�����I
�@�e�e���Ē��\�͂ɖڊo�߂�A�Ƃ����Ɓw�W���W���̊�Ȗ`���x�́u��v���v���������A���̏e�e�͓���Ȃ��̂������B�e�e�̏o�����m�F���邽�߂Ƀo���[�h�͐헐�̓���A�W�A�֔�ԁB
�@����A�W�A�^���ł̓l�I�j����сi�W�F�[���X�ɓc�j���҂��Ă����B�l�I�j�����Q�����̕ߗ����畷���o�������ɂ��ƁA�e�e�̌����͂������̏ꏊ���痈�Ă���炵���B�Q�����͂��̏ꏊ���u�R�����v�ƌĂ�ł����B�u�ǂ��ɂ���H�v�u�z�C�E�g���Ȃł��B�v�u���������s���Ă݂悤�B�v�u�o���[�h����I�{�C�ōs���C�ł����H�G�n�ł���H�v�u�`���[���[���T�[�t�B�������邩���`�`�I�I�i�ʂ̉f��j�v
�@�o���[�h�̔M�ӂɂق�����ăl�I�j���R���̓z�C�E�g���Ȃ֓��s�B�e�e�͔�ь�����A���т���Q�����͔�яo���ďP���������A�����̎v���Łu�R�����v�ւ��ǂ蒅���B�����͋����覐E�������B����V��̃}���K�w�@�������`��l�x�ɂ��A�l�ނ��ŏ��ɗp�����S��覓S�E�E�E覐���Ƃꂽ�S�����������ł���B�m���ɂ���͗��ɂ��Ȃ��Ă���B�n���ɖ��܂��Ă���n�w����@��o������قǎ����葁���B���R�ɂ��߂���覐������Ă���̘b�����B
�@�����́A�F���������覐̒��Ŗ����Ă����u�����v���푈�ɂ���Ċo�������̂��E�E�E�B
�@���̂���~���Y���т͌��d�ȊĎ��̒��A��������a�@����E���B���̑���NY����������֍s���ƁA�敨����Ɗ��łT�O�O�h���̌�����P�T�ԂłS�O���T�T�V�Q�h���P�T�Z���g�ɑ��₵�Ă��̂܂��H����i�����܂����j�B�������[�g�ׂ�ƁA�X�g�b�N�z�����A�����A�A�����J�̃E�B�`�^�S�̋�s�����ɂ��ꂼ�ꑗ�����Ă����B�ނ����[�_�[�炵���B
�@�o���[�h�͂܂��E�B�`�^�ցB�����Ńn�h���[�͍H��{�݂����A�Ȃ�炩�̋��u������Ă������Ƃ���������B���̌�n�h���[�͖��̂�ɓ�Ăŏ������B
�@�X�g�b�N�z�����ł̓R�m���@�[���Ƃ��鐻�S���ō�������̈˗������Ă����B�ނ̎���Ɋ�Â��č���������͐M�����������\�������Ă����B���ʂ̐��@�ł͗Z�����Ȃ������̍����ł���A�������d���͌��̋����̂X�O���̏d���i���蓾��̂��j�B�ނ͂���ŏ�蕨�̂悤�Ȃ��̂������肾�B�u�ނ͗D�G�����A�C�̓łȐl�ł��E�E�E�ނ͔Y��ł���B�܂�ŁE�E�E�܂�ň������Ƃ���Ă���悤���I�v
�@�����Łi���Ƃ��瓌�m�ł��邱�Ƃ��������Ă��Ȃ��Ƃ��낪�����j�o���[�h�̓��i���h�ƑΖʂ���B���i���h�͓���G���W���̐�������Ă����B�ނ͑������Ă���l����m��Ȃ������B�K�v�Ȓm���͓��̒����玩�R�ƕ����сA�K�v�Ȏ��ɑ��������̂��B�ނ͎����̈ӎv�ɔ����ĉ����ɑ����Ă���̂ł���A�ގ��g��Y���Ă����̂��B
�@�~���Y���т́E�E�E�A�����J�̂Ƃ���Z��n������Ă���ƁA���m��ʏ��N�ɐ���������ꂽ�B���N�͔ނ�����Ȃ�A�u���т���I�v�Ƌ삯������B
�u���ɉ����H�v
�u�ꏏ�ɍs���B�v
�u���ƁH�ǂ��ցH�v
�u�ǂ��ł��B�v
�u�����Ƃ��낾���B�v
�@���̂��돭�т̃A�W�g�̑O�ł́A�o���[�h�ȉ��A�������������̃����E�C���E�u���b�N�̖ʁX���ҋ@���ď��т̋A���҂��\���Ă����B
�@���̎��_�Ŕނ�̐^�̖ړI�����Ȃ̂��A���m�ɕ��������l�́i���łɌ����l�������āj�n����ɑ��݂��Ȃ��ƒf������B
|
| ��43�b |
���m��ʉF���̑����l�i��j |
�@��҂͂ǂ��������Ă��l�^�o���ɂȂ肻���Ȃ̂ŁA���e����̓I�Ɍ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�O�҂̃T�X�y���X�t���A�~�X�e���A�X�ȓW�J�͂Ȃ��Ȃ��̂��̂ŁA���������̍�i�A�l���Ă݂�����B�����b�������o�Ă��Ȃ��B����ł��Ă�����SF���̂Ȃ̂�����A����͉��o�̎������낤�B�W�F�[���X�E�S�[���h�X�g�[���ēi��\��w���E����̏��ȁx�j�̐��U�ō��̉��o�ł͂Ȃ����B
�@�㔼�������̉��o�͕ς��Ȃ����A�O�҂����E���щ�����̂ɑ��A�㔼�̓E�B�`�^�̍H����ł́A�o���[�h�~���Y����+�R�l�̑Ό������S�ł���B��҂̓��o�[�g�E�f�����@���ƃX�e�B�[�u�E�C���n�b�g�́ATV�h���}�̔��e���z�������Z����̗l����悵�Ă����B�Ȋw�͂ł͓��ꑾ���ł��ł��Ȃ��ƌ�����o���[�h�́A�S�l�̃`�[�����[�N������S����Ɏ������ނ��A�����Ń~���Y���т͂Ƃ��Ƃ����̌v��̑S�e���u�����̌��t�v�Ō��n�߂�B
�@���o�[�g�E�f�����@���͎n�I�}�������Z�ł��܂芴���\�ɏo���Ȃ����A�f���炵�����Z�������Ă����B�O�҂ł͍��Ƃ�w�����āu�F���l���ׂ��I�v�݂����Ȍ����������������̂��A���т̘b���Ă��邤���Ɋ�̌������Ă��ėD�����ʎ����ɂȂ��Ă����̂��킩��B���̕ӂ�̔����ȉ��Z�͂������ł���B
�@�܂��A�~���Y���щ�����X�e�B�[�u�E�C���n�b�g���A�A�b�v�ş�X�Ƙb��������V�[���������A�S�\�ɂ��W��炸�A�S�Ă���߂��悤�Ȕ߂����ȕ\������B
�@�v��̑S�e�Ƃ́E�E�E������ڂ�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���݂̊������炷��Ƃǂ��Ȃ̂��H�Ƌ^�����������Ȃ��B���̍l�������Ȃ̂�������Ȃ��A�u�����b�����v�ōςޓ��e�Ȃ̂�������Ȃ��A����������ɂ���Ă͌��{����l������Ǝv���B���Ɂu���̎q�B�͒n���ł͍K���ɂȂ�Ȃ��B�v�Ƃ����Z���t�͎����A����͂�����ƌ����߂��ł́H�Ǝv���Ă��܂��B�X�^�b�t�ꓯ�̑P�ӂƈӋC���݂��^�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�����łȂ���A����ȑ��ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��������낤�B
�@���̍�i�̈�ۂ́w�L���[�|���̂���X�x�����ς����Ɋ�����u���S�n�̈����v�Ɏ��Ă���B�m���Ɂw�L���[�|���̂���X�x�͉f��j�Ɏc�錆�삾�B���������̖k���N�o�q�V�[�����������C�ɂ݂Ă͂����Ȃ����낤�B�����܂ŏ����ƁA���̐S�͂������蔖����Ă��܂����̂��ȁA�Ǝv���B���̎���ɂ͂������s���A�Ȋ�����M�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂��B�ŋ߁A���B�f��w�O���ڂ̗[���x���ς����A���̉f��̒��̐l�����Ȃ�A���̍�i�����ĉ����Ȃ����������낤�B������ƌ����āA�̂͗ǂ������Ȃ��Ƃ͌��������Ȃ��B�Љ�̐��n�A�Ȋw�Z�p�̔��W�A���ꂪ�i���Ƃ������̂Ȃ̂��B
�@���������̂U�O�N��ł��A�����܂ŕ`�����̂͗E�C�����邱�Ƃ��������낤�B�S���̂��������x�g�i���A�ҕ����n���i�A�����J�����ǁj�Ɍ�������Ă��܂��b�Ǝ��邩�炾�B�����ɂ��A�����J���E�j���[�V�l�}�̖G�������̂ł���B
�@�ʐ^��ԍ��̃W�F�[���X�E�t���[���[�͂��̌�ēɓ]�����A�w�e�ۓ��}�W�F�b�g�o�X�x�w�Y���R�����{�@���҂̃��b�Z�[�W�x�Ȃǂ��B�����B
|
| ��44�b |
�F������̎g�� |
�Ƃ��閯�Ԃ̌������ɋΖ����Ă���G���b�N�i�E�H�[�����E�X�e�B�[�u���X�j�́A�t���͕������_�i�H�j�ɂ�����l�߂̕������������炸�A����҃W���l�b�g�i�Q�C���E�R�[�v�j�ɂ�����U�炷�r��閈���������B�����Ɍ������ɓˑR����Ă������R�����P����Ȃ�������̒j�i���o�[�g�E�E�F�b�o�[�j�B��l�̂���肪�ʔ����B�u��������Љ�ł͏��̖����͏o�Y�̂݁B�v�u���̂��߂ɐ����Ă���H�v�u�C�����s���B�v�u������ɓ���H�v�u�m�����B�v�u�����݂́H�v�u�������B�v�u�����͂́H�v�u�G�l���M�[���B�v�u���̂��߂ɁH�v�u�x�z���邽�߂��B�v�j�̓A�C�J�[�ƌ����A�F���l�������B�A�C�J�[�͊���Ƃ������̂�m��Ȃ��B�ނ̐��͌��Ƃ������̂̑��݂��Ȃ��A��̈ӎv�ɑS�����]���A���̂悤�ȎЉ�����B�A�C�J�[�͒�Ă���B�l�Ԃ��������邽�߂Ɋ���Ƃ������̂�m�肽���B�N�̊���ƕ��������������悤�B���̕��������Ȃ�Ƃ��Ă��m�肽���G���b�N�͂��̒�Ă��Ă��܂��B�����̎�������Ă��܂����킯�ł���B
�@������������G���b�N�͌������͂��ǂ��Ď��͔j�u�������B����A�C�J�[�̓W���l�b�g�Ɂu���Ƃ͉����H�v�ƃX�g�[�J�[�܂����ɕt���܂Ƃ��B�W���l�b�g�͂ł����l�ŁA�A�C�J�[���s�N�j�b�N�ɘA��čs�����肵�āA����̉����邩�������悤�Ƃ���B�����ł��A�C�J�[�̐��E���M���m�邱�Ƃ��ł���B�u���̎Љ���݂���Ƃ�����A�����ɂ͂��Ȃ��݂����Ȑl���H�������͂��̂�����H�v�u�Ⴂ�͂���B���ꂪ�K�����ނ��B�����҂͉Ȋw�ҁA�����҂͘J���ҁA�E�������ӂȂ畺�m�E�E�E��{�I�ɂ͊F���������B�v�A�C�J�[�͂��ꂪ�i�������Љ�ƌ����B�K�����ނ́u�Ȃ肽�����̂ɂȂ�v�Ƃ����̂Ƃ͈Ⴄ��Ȃ��B�����̋��Y��`�̃C���[�W�Ȃ�ł��傤�ȁB��̂ق����K�����ނ��ꂽ�l����������Ă��邪�A�����푰�ł������ς���Ă��܂��Љ�͋��낵���ˁB
�@�⍓�ȃ��{�b�g�Ɖ����čŏI�����W�X�ƍ���Ă����G���b�N�ƁA�n���N���ɋ^��������n�߂�A�C�J�[�Ƃ����A����̋t�]���ʔ������A���o�Ƃ��Ă͕��B
|
| ��45�b |
�F�����b���K�]�C�h |
�@���K�]�C�h�E�E�E�ȂW���p�j���[�V�����̃��{�b�g���̂ɏo�Ă������Ȗ������A�z���g�ɂ����������O���B���������͉��b�͘e���ɉ߂��Ȃ��B�ق�Ƃ̃e�[�}�́u�N���[���l�ԁv�̐���`���A�{�iSF�ł���B
�@���V���[�Y�ɂȂ��Ă���A���D�̔��l���A��l���̍��@���Z���������Ȃ��Ă����ԋC�O���ǂ��Ȃ��Ă���悤�ȋC�����邪�A����������͂Ȃ�ƁISF�����̋����N���t�H�[�h�ED�E�V�}�b�N�搶�̌��Ăł���I�b�̖��x�ɂ��Ă̓V���[�Y���ō����x���B
�@�����A�l�ނ͊O�F���ɂ��i�o�A�F�X�Ȑ��̐����̕W�{���قɏ����Ă���B���ł��������̃��K�]�C�h�͂��̋��\�Ȑ��i�A����ł��Ēm�b�����肵�����ɐB�\�͂������Ƃ����A�댯�Ȑ����������B����Ȃ킯�Ń��K�]�C�h�́A�n���Ɏ������֎~�ɂȂ��Ă����B
�@�Ƃ��낪�w���_�[�\�����m�i�����E�����f���j�͍��@�̈�p�Ɍ����̂��߃��K�]�C�h���B�����Ă���A����邻�̘S���j���Ă��邱�Ƃ�����B������ς��A�ɔ�ɓz��T���ď������Ȃ���E�E�E�����Ŕނ͎����̕����gDuplicate�@Man�h�����i���̎���A�N���[���Ƃ������t�͂Ȃ������j�A�ނɃ��K�]�C�h���E�����邱�Ƃɂ���i�ڋ����I�j�B
�@���̍�i�̍ő�̓����́A�����ɖ������E�̘b�A�Ƃ������Ƃł���B�Ȃɂ��둾�z�n�̊O�܂Ől�ނ͓��B���Ă���̂�����A���E�������͐i�����Ă��Ȃ��Ƃ����������낤�B����Ŗ��Ȗ����t�@�b�V�����▢�����z�A�����J�[�A�����C���e���A���o�Ă���B�����ɂ���邪�ASF�f����B��ꍇ�A�����t�@�b�V�����͂�قǏ��Z������������Ȃ����������B�A���ƌ����ԂɃ_�T���Ȃ��Ă��܂��A��i���̂��̂̕]���ɂ��e�����Ă��܂��B���̍�i�̕����������p���������B�����ATV�d�b���o�Ă���̂����A���̊O�ς�����̉t���p�\�R���Ɋ�Ɏ��Ă���B�������v�b�V���{�^���ł͂Ȃ��ă_�C�����������B
�@�l�Ԃ̕����͐��{�����d�ɊǗ����Ă���l����������邱�Ƃ͈�@�ł��������A�w���_�[�\���̓R�l�ō���Ă��炤�B�����͕����Ă����Ǝ���ɖڊo�߂Ă��܂��A���Ȃ��ƂɂȂ�B�L���A���i�Ƃ��ɖ{�̂ƌ������͂����A�{�̂��E�����Ƃ��邱�Ƃ�����B���̂��߃N���[���͎��������܂��Ă���i�ǂ����ŕ��������Ƃ�����ݒ肾�E�E�E�j�B�w���_�[�\���͕����̎������T���Ԃł��邱�Ƃ��m�F���Ē�������B
�@�w���_�[�\�����Q�͔����ق̒��Ŗڊo�߂�B���ɂ̓s�X�g���������Ă����B�u���K�]�C�h���E���Ȃ���E�E�E�B�v
�@��P��ŁA���Q�̓��K�]�C�h�Ɏ����������ł��邱�Ƃ�m�炳���B�u���͐l�Ԃ��I�v�u�N�͎g���̂Ẵ��{�b�g���B�v�ӊO�ƃC���e�����̉����B���R�Ƃ��釂�Q�B
�@�w���_�[�\���Ƀ��K�]�C�h�������������u���[�J�[�A�G���b�g�ɉ�i���݂���A��Ȍ����ɏZ��ł���j�B�G���b�g�͊甼���ʂʼnB���Ă���B���ă��K�]�C�h�Ɋ�������ꂽ�̂��B���̕ӌ|���ׂ����B���Q�́A�l�ƐڐG���Ă��邤���ɖ{�̂̋L������݂������Ă���B
�@���Q�͖{�̂̍ȃ��[���i�R���X�^���X�E�^���[�Y�j�ɓd�b��������B�ނ͔ޏ�����l����̌Ăі��u�v�����Z�X�v�ƌĂԁB�u�d�b�̐��A����l�Ɏ��Ă�����B�̂̂��Ȃ����B�v�Ȃɕ�������������Ƃ��ꂽ�B
�@���Q�͖{�̂ƑΛ�����B�����͈�̉��̂��߂ɐ��܂�Ă����̂��E�E�E�����ɂ������錠��������͂����I����Ӗ��A������ɑ���ًc�\�����Ăł���i��͂�ǂ����ŕ��������Ƃ�����b���E�E�E�j�B
�@�{�̂Ƈ��Q�ƃ��[���̊�ȂR�p�W�����܂��B���낤���Ƃ��A���[���͕����̂ق��ւȂт��Ă����B�u�s�v�c�ˁB��l�͌��������l�A������l�͈������l�E�E�E�v�i�m���ɂ����тꂽ�{�̂��Ⴍ�ĐV�N�ȕ��������ł��ˁj�@���łR�l�̎咣���ٔ����Ă���ԂɁA���K�]�C�h���@��ɐN���B�{�̂��燂�Q���E�𐿂��������G���b�g���N���B�����������Ă���ԂɎ����̃^�C�����~�b�g���߂Â��B�����A�ǂ��Ȃ�H�����ԍۂɂȂ��Ă������������Ă����āA�Ō�܂Ŗڂ������Ȃ��I
�@�R���X�^���X�E�^���[�Y�̓u���[�h�E�F�C�̃x�e�����o�D�B�V���[�Y���̏��D�ł͍ő�̑��݊��B�W�����E�t�H�[�h�́w�R�����x�w�o�t�@���[����x�A�T�~���G���E�t���[�́w�V���b�N�W�c�x�w���̃L�b�X�x�ȂǂɎ�����ŏo���B
|
| ��46�b |
�A���e�I���V���ւ̓� |
�@����A���e�I���V���ւ̔�s�����Ƃ��āA�������l�̉F���D�ɁA���ۂɂ������s���ԁi�Q�U�P���P�O���ԂT�P���j�A���悵�Ă��������S���I�A�g�̓I�ȃf�[�^���̂�Ƃ����͋[�������s���B��Â͐��{�����Ԃ��͕�����Ȃ����A����������팱�҂͌����̃A���e�I������s�ւ̃^�_�������炦��B�������������A���炩�̕s���̎��ԁA�g���u���͐������ꍇ�A�ً}�X�C�b�`�i�N�ł�����������ꏊ�ɂ���j��������A�����͂��̎��_�Œ��~�ƂȂ�B
�@���̎����ɎQ������팱�҂̓W���[�E�f�B�N�X�y�����i�}�C�P���E�R���X�^���e�B���j�A�A���V�A�E�w���h���N�X�l�ފw�ҁi�W���N���[���E�X�R�b�g�j�A�L�[�X�E�G���X�V���L�ҁi�����[�E�E�H�[�h�j�A�}�C�P���E�����g�A���w�ҁi�`���[���Y�E���f�B���b�N�j�A�}�V���[�E�W�F�[���X��t�i�O���n���E�f���g���j�A�w�����[�E�N���C�u�����Ԋw�ҁi�T���f�B�E�P�j�����j�B
�@�F���D�ƌ����Ă��F�����q�@�d�l�ŁA��q�͉��K�Ȋ��ʼn߂�����B�������^���̌��Ƃ��āA覐ΌQ��ʉ߂����肵�ď�q�ɗh���Ԃ��������B�ŏ��͏��F��蕨�ƍ����������Ă����팱�҂����A�������Ȃ��Ƃ����X�ƋN����B�钆�Ɏ�����߂���A�Ȃ������̂ʂ�����݂������ɒu���Ă���B���炩�ɉ�X�ȊO�̃��m������E�E�E�ϑz���Ǝv���Ă����������ł͂Ȃ��I�����ł̋^�S�ËS�ƌǓƊ�����l�X�̐��_�͕s����ƂȂ�A�e�l�̉B���ꂽ�g���E�}���I�ɂȂ��Ă����̂ł������B�l�ԊW�̃O�_�O�_�����_�ɒB�����Ƃ��A�����Ƌ������B���I
�@���������Ēn���Șb�����A���ꂼ��̃L�����N�^�[�͖ʔ����B���ɂ����킪�܂܌����Ă���g���u�����C�J�[�̃}�C�P���E�R���X�^���e�B���͂͂܂���B���{�Ō����w�z���S�S�P�~�h���x�̋��q�M�v�݂����Ȗ��ǂ���B
|
| ��47�b |
�o�[���卲�̔]�זE |
�F���J�����{�i�I�Ɏn�����鎞��A�R�͈�̕ǂɓ˂��������Ă����B�F���ɂ����ĕ��ʂ̃R���s���[�^�[�ł͕s���̎��ԂɑΉ��ł��Ȃ��B���Ƃ����ĉߍ��ȉF����ԂŐ��g�̐l�Ԃ̊����͌����Ă���B���u����͊O�F���ł͎��Ԃ�����߂��B�������l�Ԃ̔]�𓋍ڂ����R���s���[�^�[������Ă͂ǂ����A�Ƃ������ƂɂȂ�B�����ŗD�G�����s���̕a�ŗ]���������������i�s���ǂ����I�j�Ƃ����o�[���卲�i�A���\�j�[�E�A�C�X���[�j�ɐ���������B����������������ʂƌ����Ă�����Ȏ�������������l�����Ȃ��Ǝv���̂����A���l�̉�����W�F�j�t�@�[�i�G���U�x�X�E�y���[�j������ɂ�������炸�A�o�[���卲�͏�������B�V�˂���������o�[���卲�́A�S���������F���J���Ɉُ�Ȗ������������̂��B
�@���������̌v��A�@���I�ɂ͂ǂ�����̂��낤�B�u���v�Ƃ������Ƃɂ���̂��B�]�t�R���s���[�^�[�Ƃ������ƂŊ함�Ƃ������ƂɂȂ�̂��B
�@�u���炷��ō��̓��]�ɂȂ邩�������A�F���̓���������]�ɂȁB�v�u�_���������邩������܂���B�v
�@�]�����ɂȂ����o�[���卲�͊J����ԁu�ɂ��B�v�ƌ����̂����A����͌����ɋ߂��̂ł͂Ȃ����B����N���̒Z�҂ł��]�����ɂȂ�j�̘b�����邪�A����̓]���Ƃ����B������͉����A���o�A���o���d�q�I�Ɍq���Ă���̂Ŕj�i�̑ҋ��ł���B
�@�`�[���̈�l�A�S���w�҂̃}�b�L���m�������i�O�����g�E�E�B���A���X�j�͂��Ƃ��Ƃ��̌v��Ɉق������Ă����B�u�����͕����I�ɑ̂ƂȂ����Ă��āA�g�̓I�~������������A����������A���]�����肷��̂ł��B�v�܂�S�Ɛg�͕̂ʕ��ł͂Ȃ��A�⊮�������Ă���B�g�̂Ƃ����g�i�����j������������ꂽ�]�́A������v�����܂܂Ɋg�債�Ă��܂��B���܂܂Ől�ނ��Ȃ����Ȃ��������_�̗̈�ɒB����̂ł͂Ȃ����E�E�E�B��̉����N���邩������Ȃ��A���������x�����낤�B���������w�A���^�[�h�E�X�e�[�c�x�Ƃ����f��ł́A��d�̍����t�̂̓������J�v�Z���Ƀv�J�v�J������ł�����h�����������������ґz����Ɣ]�̉B���ꂽ�\�͂��o������A�Ƃ����̂����������A������[���u�]������ԁv�ƌ����邩������Ȃ��B�ŋ߂̃T�C�o�[SF������ƁA�u�]����������Ȃ��́H�v�Ƃ����������ӎ��̊g��ɍm��I�Ȍ���������̂����A���̎���A�l�Ԃ̐��_�͂����炭����ɑς���ꂸ���ł���ł��낤�Ƃ����ߊϓI�ȍl���̂ق������������B
�@�ŁA���̕s���͓I������B�Ƃɂ����o�[���卲�A���͂œ����Ȃ��̂ɂ������ԓx���傫���Ȃ�A���ߌ����ɂȂ�B�u���ɔY�݂ȂǂȂ��A����͐l�ԓ��L�̂��̂��B�ǂ�A�N�̔Y�݂��Ă�낤�B�y�ɂȂ邼�B�v�A���e�i�Ől�̉�b�𗧂��������Ă���l�q���|���B
�@�e����ɗ]�T������̂ŁA�]������đ傫���Ȃ�B�u�e��������Ƒ傫������B����Ȃ������ɂȁB�v�قǂȂ����Č��������W�F�j�t�@�[�ɏP���|����Ƃ��������������B�����͕s�������A�o�[���]�ɊW����ƌ����}�b�L���m���͌x�����邪�A�Ȋw�҂͎���݂����o�[���]�̈琬��簐i����B�o�[���卲�̖\���͂Ƃǂ܂�Ƃ����m�炸�A�}�b�L���m���ƃW�F�j�t�@�[���ڋ߂��Ă��邱�Ƃ��@�m�����o�[���卲�́E�E�E
�@�ނ̔\�͊g��̌����͂�������ւ̎����S�������Ƃ����̂��������B
|
| ��48�b |
�\�b�Ԃ̖��� |
�@�ŏI��ڑO�ɂ��āA����܂����̂�������i���o��B���ꂾ���̒�͂�����̂�����A�����Ƃ�ꂽ�̂ł́E�E�E�܂������ɂ����B
�@�Ȃ�ƍ���͒m���Ă���l�͒m���Ă���A�m��Ȃ��l�͂܂������m��Ȃ�SF�f��̋����A�C�u�E�����L�I�[���ēi�I�[���V�l�}�@�I�����C���ł́w�����L�I�[�x�ƕ\�L�j�̌��āA�r�{�ł���I�����L�I�[���ē͂T�O�`�U�O�N��AB��SF�f�����葱�����B�w�o���p�C�A�̘f���x�w����A���[�o�̘f���x�ȂǁA�ނ̍�i�́A��\�Z�A�`���`�ȓ��B�ł��A�m�ł���SF�}�C���h������Ίӏ܂ɑς�����f�������Ƃ������Ƃ��ؖ����Ă���B���Ɂw���n���l�Ζ������l�x�i����w�^�C���g���x���[�Y�x�j�͎��ԗ��s�̕��@�A�������E�̗l�q�A�Ȃǎ��Ƀ��j�[�N�ŁA���Ƀ��X�g�̈ӊO������ې[������ł���B
�@���́w�\�b�Ԃ̖����x�́w���n���l�Ζ������l�x�̃��X�g����̒��z�ł��낤�B
�@�`���A�w���m�ُ̈�Ȉ���x�̃t�@�[�X�g�V�[���̂悤��B52����s���Ă���BB52�̕З��ɏ��^��s�@���Ԃ牺�����Ă���B�������@�̃e�X�g��s�ł���B�p�C���b�g�̃W���i�f���[�C�E�}�[�`���j���{�^���������ƁA�@�͐����悭B52���痣��Ă������B����͂Ȃɂ��̋L�^�f�悩��̉f�����Ǝv�����A���͂�����B���ł͍Ȃ̃����_�i���A���[�E�}�[�t�B�[�j�������Ԃŋ@��ǂ��Ă���B�����g���u�������I�@�̓����_�̎����Ԃ̖ڂ̑O�ŕs�����A�����Ԃ͒E�ցA��l�Ƃ��ӎ��������B�W�����C�����ċ@����~��Ă݂�ƁE�E�E�������Ⴄ�E�E�E�Â��������B�l�������������Ă��Ȃ��B�����Ŏ~�܂��Ă邶���I
�@�W���ƃ����_�ȊO�A�S�Ă��Î~���Ă����B��X�͎��̂��E�E�E�H��n�Ŗ߂��Ă݂�ƁA��͂��n�̐l�Ԃ݂͂ȁw�]���������̗D��Ȑ����x�̂P�V�[�����A�o���^�����l�ɗⓀ�����𗁂т���ꂽ���̂悤�ɐÎ~���Ă����B�������W���͊�n�̎��v���ώ@���A�������������B�ė��̃V���b�N�œ�l�͏\�b��̐��E�ɔ�яo���Ă��܂����̂��B�����Ď��Ԃ̗ڂɂ͂܂��Ă��܂����B��l�Ɛ��E�͕ʂ̎��Ԏ��œ����Ă���E�E�E�ڂ̑O�Ɍ����ꂽ���E���L�����Ă���ɂ��ւ�炸�A������������A�����͂��Ȃ��B��ΓI�ȌǓƂł������B���������v���悭����ƁA������蓮���Ă����B�l�Ԃ�������肾�������ē����Ă���B
�@������ăX�e�B�[�u���E�L���O�́w�����S���A�[�Y�x�Ɏ��Ă���Ǝv�����C�̂������B���Ƃœ�̉��l���o�Ă�����B
�@�Ƃ肠�����ǂ��������ۂ��͔c���������A��n�łƂ�ł��Ȃ����i������B��n�̑������ɂ������Ă��������O�֎ԂŗV��ł���B���̎��p�ɂ͌R�p�g���b�N������B���̃g���b�N�̓n���h�u���[�L�������Ă��Ȃ��I���[�^�[�͂T�L�����炢�������Ă���B�܂肠�Ɛ��b�Ŗ��l�̃g���b�N�͖���瀂��Ă��܂����낤�E�E�E�B���Ԏ����Ⴄ�̂ŁA���̐��E�̂��͉̂���������Ȃ��B����ɂ��Y���Y���i��ł����g���b�N�B�ނ�͈����閺����������̂��E�E�E�A���̐��E�ɖ߂��̂��H
�@����N���̏����̍�i�w�������x�Ɏ��Ă��邪�A����͓���搶�̕�����B�ŋ߂ł͕����A�j���Łw�T�C�{�[�O�O�O�X�x�ɂ������悤�Șb�����������B
�@��͂茩���͎̂~�܂��Ă���\�����@���낤�B����������w�}�g���b�N�X�x�́u�}�V���K���B�e�v�ŎB��邪�A���̍�i�͎ʐ^�Ǝ~�܂��Ă鉉�Z�̃~�b�N�X�ʼn��Ƃ�������B�q���ɂ���~�߉��Z��v������Ƃ͐��ɋS�i����قǂł��Ȃ����j�B���̎q�A�u���u���k���Ă܂��B�ʐ^�̐l�ԂƓ����Ă����l���������t���[���ɔ[�܂��Ă���V�[�������邪�A���@�͗ǂ�������Ȃ��B�Ђ���Ƃ����瓙�g��̐l�̎ʐ^��p�ӂ����̂����m��Ȃ��B
�@���A���[�E�}�[�t�B�[�̌o���́A���h���t�E�}�e�i�w�n���Ō�̓��x�j�A�X�^�����[�E�N���C�}�[�A�m�[�}���E�W���C�\���A�T���E�y�L���p�[�ƁA�₽��ēɌb�܂�Ă���B |
| ��49�b |
�F���ʐM�r�n�r�I�I |
�@���{�t�߂��s���������A���@���䕗�ɂ܂����܂�C��ɕs�����A�N���[�̂T�l�͋~���{�[�g�ŒE�o����B�����ōr���C�̃X�N���[���v���Z�X���w�i�ɕ`�����܂�A�Ȃ��Ȃ����͂�����B�����������̃V���[�Y�ŊC���o�Ă��邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������ȁB
�@�Z��������Ă���Ɖ��ɂ͊C�͂Ȃ��A����������Ȍ������̒����Ƃ������ƂɋC�����B���l�������B�����͂ǂ��Ȃ̂��A���҂������������̂��A���̂��߂̂��̂Ȃ̂��E�E�E�܂�����������Ȃ��B���X�ɑ�������Ӗ��s���Ȏ��ԁA�����@�B�A�p�j����s��`�����B�ނ�͂�������E�o�ł���̂��E�E�E�H
�@�w�A�E�^�[�E���~�b�c�x�ŏI��͂��Ȃ�n���ȓ��e�ŁA���G�ȃX�g�[���[�ł��Ȃ��B���������̘b�ɂ́w�A�E�^�[�E���~�b�c�x�̃e�[�}���Ïk����Ă���̂ł͂Ȃ����B
�@���̘b�́A�n�I�ނ�̎��_�݂̂Ō���Ă���B�ނ�ɂ͒m�炳��Ă��Ȃ����A��X�̕��ɂ���������ޗ��Ƃ������̂͂Ȃ��B��ʂɏo�Ă������ہA�����I�ɍ쓮���Ă���@�B�̖ړI��ނ�ƈꏏ�ɐ�������B
�@�ނ�͐F�X�Ȏ肪���肩�炱��͉F���l���n�����ɗ������l�T���@�ł͂Ȃ����Ɛ��������A�����ɂ��Ȃ��F���l�ƃR���^�N�g���Ƃ낤�Ǝ��݂�B���������̐������^���Ƃ͌���Ȃ��B�����͐l�̌������L�ۂ݂ɂ���̂ł͂Ȃ��A�����̓��ōl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�����v���ɁA�w�A�E�^�[�E���~�b�c�x�ɂ͋��ʂ���e�[�}���������Ǝv���B����͐��̒��A�����͑��ΓI�Ȃ��̂ł���A��ΓI�ȉ��l�ς͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�F���l���猩�āA�n���͂ǂ������Ă���̂��A�������猻��͂ǂ�������̂��E�E�E���������يE����̎��_��݂��邱�Ƃɂ���āA��X�͕��i�̉��C�Ȃ��s�ׂ�A���ʂɕ�炵�Ă����Љ���ُ͈�Ȃ��́A���ɑf���炵�����̂������A�Ƃ������������邾�낤�B�����������l�ς̋t�]��A���_�̉ߌ��ȓ���ւ�������SF�̑傫�ȓ����ł������B
�@�܂��A�u�Ԏ��v�Ńn���E�b�h��ǂ�ꂽ�l������TV�̕��֊������ڂ��Ă��������Ƃ��A�u�Ӌ�����̎��_�v�����̃V���[�Y�ɗ^�����B
�@������́A�Ȋw�I�Ȃ��̂̍l����O�ꂵ�����Ƃł���B���̃V���[�Y�̋Ȃ܂ł̉Ȋw�ɑ���M��������B���E�̓�⍢��͉Ȋw�̗͂ʼn����ł���A�Ȋw�����W����ЊQ�A�o�ϕs���A���ʂȂǐl�ނ��s�K�������ł���A�ƌ����M���Ă���̂ł���B�Ȋw�̖\���Ŕj�ǂ�����Ƃ����b���肶��Ȃ����Ǝv���邩������Ȃ����A���{�ɂ͑傫�Ȏ����ɗ����������Ȋw�҂̗E�p���`�����B�Ȋw�I�Ȏv�l��������������̃I�J���g�u���ł͂Ȃ��B
�@�v���ɂ��ꂪ�����́i�����猩��j�Â��悫�A�����J�̖����`���_�������̂��낤�B�ŋ߂̑S���E�I�ɖ������鐭���I�A�����I�s���e������ɂ��A�v���Ή����ɗ��Ă��܂����Ȃ��Ƃ����C�����܂��i�܂����̎��������ɕ�������炸���������������������킯�ł����j�B
|